
近くの水道屋さんが見つかる
ポータルサイト
おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載



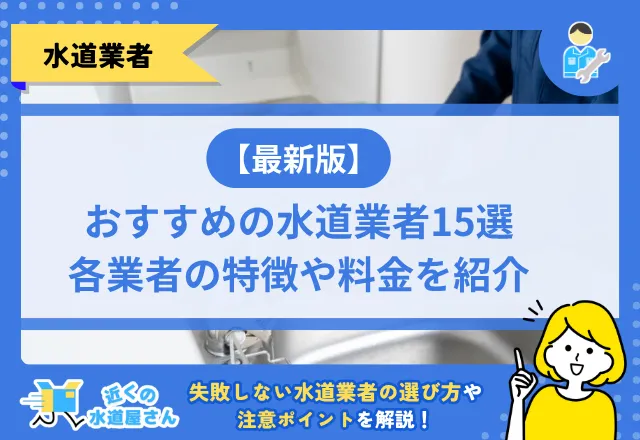
冬になると、マンションの水道が急に使えなくなって困った経験はありませんか?
特に朝の忙しい時間に「水が出ない!」と焦るのは、本当にストレスですよね。
水道管の凍結は戸建てだけの問題と思いがちですが、実はマンションでも決して他人事ではありません。
配管の構造や管理の違いから、マンション特有の凍結リスクや対処法があります。
 ビアス
ビアスそこでこの記事では、マンションで起こる水道管凍結の原因や、予防策、凍結時の正しい対処法をわかりやすく解説。



凍結対策の方法や凍結の解消法についても紹介するで!
水道管の凍結について詳しく知りたい人はぜひ最後まで見たってや!


マンションの水道管凍結は、戸建てとは少し異なる理由で起こります。
一般的に、水道管が凍るのは配管内の水が低温にさらされて氷になることで、水の流れが止まってしまうことを指します。
マンションでは以下のような特徴が凍結リスクに影響を与えています。
マンションの配管は多くの場合、壁や床の中に埋め込まれているため、外気の影響は直接受けにくいと思われがちですが、実際はそうとは限りません。
特に、最上階や最下階の一部の部屋では、外壁に近い配管部分や屋外に露出している部分が冷気にさらされやすくなります。
マンションは共有部分の配管があり、管理組合や管理会社がメンテナンスを行いますが、専有部分の配管は住戸ごとの管理となります。
このため、凍結予防策が十分でない専有部分の配管で凍結が起きやすくなります。
長期間水を使わないと配管内の水が動かず、凍結しやすくなります。
特に冬場に長期間留守にする場合は注意が必要です。
水道管が凍りやすいのは、主に以下のような条件がそろったときです。
密水は凍ると体積が増える性質を持っています。閉された配管の中で水が氷に変わると、内側から管を押し広げる強い圧力が発生します。
この圧力に耐えきれない場合、管にヒビが入り、最悪の場合は破裂してしまいます。
特に凍結→解凍のタイミングは要注意。朝、気温が上がってきて氷が溶けると、氷の奥にたまった水が一気に噴き出し、漏水が起きるというケースが多く見られます。
1つ目は、外気温がマイナス4℃以下になることです。
「水は0℃になると凍る」というイメージがあるかと思いますが、水道管の中の水が実際に凍り始めるのは「マイナス4℃以下」が目安になります。
関東や西日本でも、雪が降るほど冷え込む日がシーズン中数回はありますよね。
「水道管まで凍るわけがない」と思っていても、実際に凍結するリスクはあるのです。
冬の寒い時期に長期間水を使わないことも、凍結のリスクが高まる要因です。
水道管の中の水が動かずにずっと溜まっていると、流れている状態よりも凍結しやすくなります。
最高気温が0℃を超えない日を「真冬日」と言いますが、寒い地域では最高気温・最低気温ともにマイナスということもよくある話です。
最高気温が高ければ日中に水道管内の水も温まりますが、日中でも気温が上がらなければ当然、凍結するリスクは高くなります。
凍結によって配管が破裂した場合、以下のような被害が想定されます。
また、露出している部分からの漏水は水道料金の減免対象にならない自治体もあります。修理費だけでなく、見えない損失も大きくなることがあります。


マンションで水道管の凍結を防ぐためには、まずは日常生活の中でできる簡単な対策から始めることが大切です。
ここでは、実践しやすい基本的な凍結予防策をご紹介します。
マンションの水道管の中でも特に凍結しやすいのは、外気に接しているバルコニー側や最上階の配管、そして共用部分の配管です。
これらの露出部分には、市販の保温材や保温テープをしっかり巻きつけることで熱を逃がさず、凍結を予防できます。
管理組合がある場合は共用部分の保温状況も確認し、必要に応じて相談するとよいでしょう。
まずは日が当たらない・風当たりが強い場所です。
具体的には次のような場所が考えられます。
日が当たらないと、想像以上に気温は下がりやすくなります。
日が当たる場所に水道管があれば、夜から朝にかけて冷えても日中にある程度温められるため、凍結まで至る可能性は低くなるでしょう。
これに対し、日が当たらない場所では日中の間に水道管が十分に温められず「凍結しやすい状態」になり、夜〜朝に凍ってしまいやすいのです。
また、風当たりが強い場所ではマイナス1〜2度程度でも凍結する恐れがあるため注意が必要です。
水道管の多くは地中や床下、壁の中にあります。
しかし、マンションの屋上のタンクまわりなどでむき出しになっている水道管もまれに存在します。
建物の外壁などに接していると外気の影響を受けやすいため、凍結の危険性が高くなるのです。
庭や駐車場など、屋外で水道を使用するための立水栓も、凍結しやすい場所だといえます。
立水栓は地中に埋まっておらずむき出し状態なので、地表面の気温に影響されやすいのです。
使用するたびに水道管内の水が抜けるため、再び水を出そうとしても水道管内に水がたまっていない場合があり、そのまま水が凍結してしまうことがあります。
また、意外ですが給湯器も凍結しやすい場所のひとつです。
給湯器は水道管からの水を沸かすための機械のため、水道管に直接接続されています。
そのため配管の中には使用後も水が残っている、というのが理由のひとつ。
もうひとつは、給湯器が屋外にあるとつながっている水道管もむき出しになるので、連動して凍結しやすくなることが原因です。
寒波が訪れ、気温が氷点下になる予報が出た際は、蛇口をほんの少しだけ開けて水を流し続ける方法が有効です。
流れる水は凍りにくく、水道管内の水が停滞するのを防ぎます。
ただし、水道料金が気になる場合は、流す水量を最小限に抑えつつ、配管が凍結しないよう調整しましょう。
マンションの一戸建てと違い、配管が壁や床の中に隠れている場合もありますが、室内の温度が極端に下がると配管周辺も冷え、凍結のリスクが高まります。
特に冬季は暖房を適度に使用し、最低でも室温が5度以上になるように心がけましょう。
寒い部屋に設置されている給湯器周辺などは重点的に暖めることをおすすめします。
長期の外出や旅行でマンションを空ける場合、給水元栓を閉めて配管内の水を抜く「水抜き」を行うことが重要です。
これにより、水が凍って膨張し水道管が破裂するリスクを大幅に減らせます。
水抜きの方法はマンションの設備によって異なるため、管理会社や専門業者に相談して正しい手順を確認しましょう。
まずは水道管の凍結対策を5つご紹介します。



寒冷地に指定されている地域では寒冷地仕様の設備がマストです。
寒冷地仕様の水回り設備について気になる方はこちらの記事も


さきほど、凍結してしまったときにタオルやカイロで温めたように、保温材を使って水道管を寒さから守ることも有効です。
一般的には次のような断熱材が使われ、専用の商品も市販されています。
これらの素材でできた保温材を使うことで水道管の表面温度を上げれば、凍結の予防につながります。
内側が保温材、外側が塩化ビニールになっている素材であれば、外で使っても雨から守ってくれるため便利です。
費用を抑えたい場合は使い古したタオルを巻き、ビニールテープでおさえるという簡易的な処置でも一定の効果は得られます。
雨や雪にも対応できるよう、ビニール袋などをうまく利用しましょう。
水道管だけでなく、蛇口にも保温カバーをつけるのがおすすめです。
蛇口用の凍結防止・保温カバーとして、ホームセンターなどで市販されています。
また、コックヒーターという名前の蛇口用のコンパクトなヒーターもありますよ。
気温がマイナスになることが多い地域なら、凍結防止ヒーターを使うのも有効です。
水道管にあらかじめ専用のヒーターを巻きつけておくことで、冬の間はスイッチを入れて常に水道管を温めておけます。
当然ながら、それだけ電気代はかかるので注意は必要です。
旅行で家をあける・特に冷え込む前日などは、水抜き栓を利用して凍結を防ぎましょう。
水抜き栓はその名のとおり家の中の水道管から水を抜くための装置で、寒い地域の住宅には標準で設置されています。
あらかじめ水道管の中から水を抜いておけば、凍結してしまう心配もなく、もっとも効果的な方法です。
使い方は難しくなく、バルブやハンドルを右回りに最後までまわして水を抜き、また水を通したいときは左回りにまわすだけです。
手動式のほかに電動式もあります。
ただし何度も行うとその分手間がかかることや、水を抜いている間は水道も使えない点には注意しましょう。
つぎに、水道管の凍結を起こさないための点検ポイントを見ていきましょう。
むき出しになっている水道管があれば、風や寒さから守るために保温材を巻くなどの対策が必要です。
屋内はもちろん、屋外にむき出しの水道管がある場合は優先的に対処しましょう。
「すでに保温材を巻いてあるから大丈夫」と思う場所も、あらためてチェックしてみましょう。
もし保温材やカバーが破れていると効果が薄れたり、保温効果がなくなったりしてしまいます。
消耗品なので定期的なチェック・交換がおすすめです。
水抜き栓は水道管から水を抜いて凍結を防ぐための装置ですが、いざ使おうと思ったときに異常があっては困りますよね。
住宅に水抜き栓が設置してある場合は、定期的に点検を行いましょう。
日常的な対策に加えて、もう一歩踏み込んだ工夫を取り入れることで、より確実に水道管の凍結を防ぐことができます。
特に、寒冷地や築年数の古い住宅では、追加の設備や工夫が大きな安心につながります。
外気の影響を受けやすい場所には、自己温度制御型のヒーター線や電熱ケーブルの設置が有効です。
これは水道管に沿って設置する電熱線で、寒くなると自動で発熱し、管の温度を一定に保って凍結を防ぎます。
電源が必要ですが、電気代は意外と少なく、一晩中つけていても数十円程度のランニングコストです。
特に給湯器の配管周りや、北側の外壁近くの管にはおすすめです。
床下や壁内の通気口から冷気が流れ込むと、屋内の配管でも凍結することがあります。
以下のような調整で、冷気の侵入を抑えられます。
ただし、長期間の通気遮断は結露やカビの原因になるため、期間を限定して行いましょう。
最近では、スマートホーム化の一環で温度センサー付きのIoTデバイスを使い、配管の温度をモニタリングできる商品も登場しています。
別荘や空き家など、普段人がいない場所でも、凍結の兆候を早期に発見することができ、トラブルの防止につながります。


万が一、マンションの水道管が凍結してしまった場合は、迅速かつ冷静な対応が重要です。
正しい対処を行わないと、管の破裂や水漏れなど、さらに大きな被害につながることがあります。
ここでは、凍結が判明した際に取るべき具体的な行動を段階ごとにわかりやすく解説します。
原始的な方法ですが、気温が上がってくる日中まで待つという方法です。
気温が上がれば自然に凍結が解けるため、追加の費用や準備も必要なく、水道管が傷つく心配もありません。
ただしどれくらい待てば解けるという確証はなく、気温が上がらなければ状況が長引く可能性もあります。
また凍結した状態で長く置いてしまうと、水道管の破裂を引き起こすリスクが高まります。
そのため時間のあるときや、しばらく水を使わなくても困らない状況のときに試すのがおすすめです。
50度ほどのぬるま湯をタオルにしみ込ませて水道管に巻きつけたり、ぬるま湯をゆっくりかけたりして温める方法です。
タオルで包んだ水道管の周りに熱がじんわりと加わり、凍結した水を溶かすのに役立ちます。
途中で何度か蛇口をひねってみて、水が出るか確認しながら続けましょう。
お湯を沸かしたり、冷めたら巻き直したりと手間はかかるものの、手軽にできて軽い凍結であれば早く解消しやすいのがメリットです。
お湯をかける場所は、蛇口やメーターの両側にあるパイプ部分です。
破損につながるため、間違ってもメーターにはかけないでくださいね。
ぬるま湯とタオルを使うのと同じ原理で、カイロを水道管にあてるのも有効です。
水道管周辺の温度を上げることで凍結解消をうながし、放置しておけるのも嬉しいポイント。
ただし凍ってしまった場所や量によっては、たくさんのカイロを消費する可能性もあります。
また、温めすぎて火災や火傷などを起こさないよう注意しましょう。
ドライヤーの熱風を水道管にあてることで、凍結を解消する方法です。
強力な熱風を出すことで解けやすくなるものの、火気には注意してください。
また持っているドライヤーのパワーによっては、あまり効果がない場合もあるため注意しましょう。


反対に、水道管が凍結したときにやってはいけない対処法は次の2つです。
慌てていると深く考えず、ケトルのお湯を直接かけて解かそうとしてしまうかもしれません。
しかしガラスのコップに熱湯を注ぐと割れてしまうのと同じで、急激な温度変化によって水道管が破裂する可能性があります。
また塩化ビニール製の水道管の耐熱温度は70〜80度程度のため、熱湯によって水道管の損傷を引き起こすことも考えられます。
さらに火傷の恐れもあり、危険しかないので絶対にやめましょう。
あくまで使用するのは50度程度のぬるま湯にし、直接ではなくタオルにしみこませて温めるようにしてください。
水道管だけでなく蛇口まで凍ってしまったときは、開けようとしても蛇口が動かないことがあります。
寝起きなど凍結に気づかないまま無理やり開けようとすると、内部のゴムパッキンが破損してしまう可能性もあります。
蛇口も水道管同様、タオルやカイロなどで少しずつ解かすようにしましょう。
冬場の水道管凍結対策として、「水を少しずつ流し続ける」という方法がよく紹介されます。
これは、一戸建てや低層住宅で効果的な対策ですが、高層マンションや集合住宅では同じ方法が当てはまらないことがあるので注意が必要です。
水道は地上の水道管から直接供給されているため、少量の水を流し続けることで管内の水の滞留を防ぎ、凍結を防止できます。
水が常に動いていることで、凍結しにくくなるのです。
高層マンションでは屋上に設置された貯水タンクとポンプによって給水されており、水は一旦タンクに貯められてから各戸へ送られています。
そのため、水を流し続けると貯水タンクの水が減少し、もし停電などでポンプが停止した場合には断水リスクが高まります。
つまり、無理に水を流し続けることはかえって危険を招く可能性があるのです。



高層マンションにお住まいの方は、事前に浴槽や洗面器に水をためておくことが推奨されます。
また、建物の管理会社や管理組合の指示に従い、適切な凍結防止策をとることが大切です
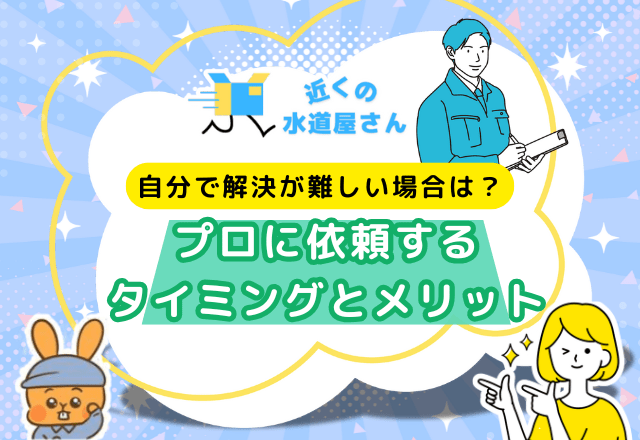
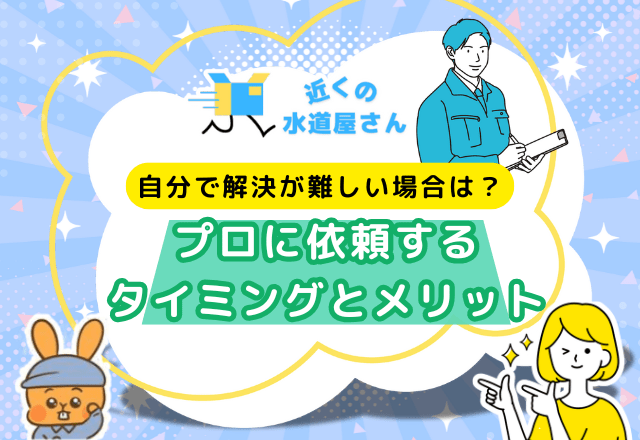
どうしても解けないときは、水道修理業者に頼んで解凍してもらう方法もあります。
これは電気解氷機や高温スチーム機を使用して解凍を行うもので、費用はおよそ8,000円〜20,000円程度が相場です。
ただ「水道管を温める作業」としてはやることはそう変わらないので、業者に頼むのは最後の手段にして、まずは自力で対処してみるのがおすすめです。
以下のような状況では、自力での対応はリスクが大きいため、速やかに水道修理業者へ連絡しましょう。
賃貸住宅で水道管が凍結した場合は、すぐに大家さんや管理会社に相談しましょう。
気が引けるかもしれませんが、放置して水道管の破裂など大ごとになっては元も子もありません。
大家さんや管理会社は多くの場合、水道管の凍結を防ぐための対策や、凍結が起こった場合の対応方法について知識や経験が豊富です。
さらに修理業者の情報も持っている場合が多いため、素人が下手に対処するよりもよほど力になってくれるでしょう。
専門業者を呼ぶとなると、修理費用や相場が気になりますよね。
水道管が破裂した場合、次のような要因によって費用は大きく変動します。
そのため一概には言えませんが、一般的には数万円〜数十万円かかると思っておいたほうがいいでしょう。
修理内容別の費用・相場は次のとおりです。
水道管の凍結・破裂による修理費用は、トラブルの内容・場所・規模によって大きく異なります。以下はあくまで目安です。
| 修理内容 | 費用・相場 |
|---|---|
| 水道管の補修(見える場所) | 20,000円〜 |
| 水道管の補修(外から見えない場所) | 30,000円〜 |
| 水道管の部分的な交換 | 50,000万円〜150,000円 |
| 水道管の全面的な交換 | 200,000円〜500,000円 |
| 壁や床の修復 | 50,000円〜300,000円 |
※早朝・夜間・悪天候などの時間外対応や出張費が別途かかる場合があります。
水道管が破裂して水漏れが起きると、被害が家具・家電、壁や床にまで及ぶことがあります。
業者を呼んだら数十万円を請求された…というケースは珍しくありません。
そんなとき、修理費用・料金を軽減する方法がいくつかあるため見ていきましょう。
自治体によっては、水道料金の減免制度が設けられている場合があります。
「対策をとっていたが破裂してしまった」など、自分に非がないと認められた場合、水道料金の減免が認められる可能性があります。
また収入や世帯構成に応じて減免されることもあるので、一度自治体や水道局に問い合わせてみるのがおすすめです。



この減免制度を適用するためには色々な条件があるけれど、まず第一条件として水道局指定工事店に修理してもらう必要があるで!
水害によって家屋に被害が発生した場合は、火災保険で補償される場合があります。
火災保険は家屋に対する火災や地震、自然災害などによる損害をカバーする保険です。
このうち台風や大雨など、水害による被害も含まれることがあり、火災保険の種類によっては補償される可能性があります。
保険料や免責金額によっても金額が異なるため、契約内容をよく確認してみましょう。



火災保険は、加入している保険内容が重要やで!
今は凍結が起きていなくとも念のため、改めて保険内容を一度確認するようにしてみてや。
当サイトでは、地域別の信頼できる水道業者を比較・紹介していますので、急ぎの際はぜひご活用ください。



水道局指定とあっても、どの水道局から指定を受けているのか不明瞭な業者には注意してや!



各都道府県の水道局指定工事店を掲載しています。
水道業者選びに迷ったときはぜひ参考にしてみてくださいね!





水道管の凍結に関してよくあるQ&Aをまとめました!



時間に余裕のある人はぜひ最後まで見たってや!
水道管の凍結が頻繁に起きる繁忙期はいつですか?
冬の12月~2月が最も水道管の凍結事故が起きやすい時期です。
水道業者への凍結解凍依頼も続出するため、連絡をしても訪問は数日後になる等すぐに対応してもらえないことがあります。
自分でできる凍結対策を取り、水道管の凍結を未然に防ぐ予防をおこなうことが大切です。
賃貸物件で水道凍結が起きたら責任は誰が負いますか?
基本的に水道凍結は入居者が責任を負うことになります。
賃貸物件では、設備の老朽化が原因のトラブル以外は基本的に入居者に責任があると見なされます。
しかし寒冷地であれば周知ですが、寒冷地に指定されていない地域にお住まいの場合は水道凍結の防止策について伝えられてないことが多いはずです。
その場合は管理会社・大家さんが負担するケースもありますので、凍結が起きたときはまずは連絡を最優先に行いましょう。


本記事では、水道管の凍結の原因や凍結したときの対処法、凍結させないための対策についてお伝えしました。
雪国に住んでいる人間にとって、水道管の凍結は決して他人事ではありません。
気温がマイナス4度を下回るような日が続く場合、保温カバーやヒーターを使うなどして対策しておくのがおすすめです。
もし凍結してしまった場合は、ぬるま湯につけたタオルを巻くなどしてゆっくりと温めるようにし、熱湯を直接かけたりしないようにしてください。
2018年の冬には、大寒波によって関東でも水道が凍る例が相次ぎました。



凍結が起きやすい場所や条件、凍結時の解消方法をあらかじめ把握しておき、慌てず対処できるよう準備しておきましょう!



水道凍結が起きて困ったときや、水道凍結によって水道管にトラブルが起きたときは僕ら水道修理業者に相談してな!