
近くの水道屋さんが見つかる
ポータルサイト
おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載



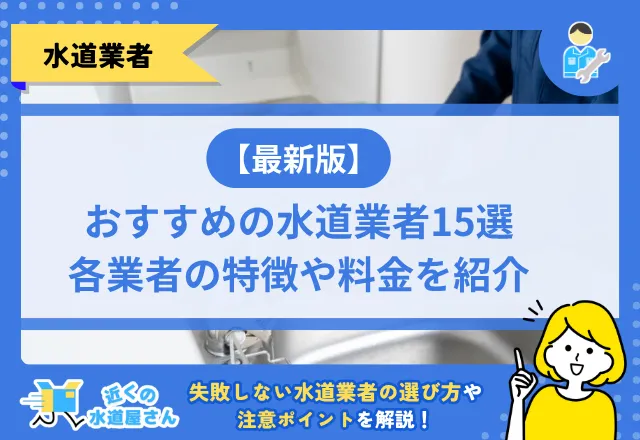
夜中にふと洗面所へ行ったら、排水口のあたりで黒い虫が跳ねていた——。
「もしかしてコオロギ?」「どうして水回りに?」と驚く方は多いでしょう。
実は、排水口から虫が上がってくるのは珍しい話ではありません。
湿気やぬめりが多い水回りは、虫にとって快適な環境です。
さらに、配管の隙間や封水の切れ目を通じて下水側から侵入してくるケースもあります。
 ビアス
ビアスこの記事では、排水口からコオロギ(あるいはそれに似た虫)が出てくる原因について考えられる理由を解説しています。



今日からできる予防・対策、そして「業者を呼ぶべき状況」をわかりやすく整理しているで!排水口から虫が這いあがってきて不安な人はぜひ最後まで見たってや。
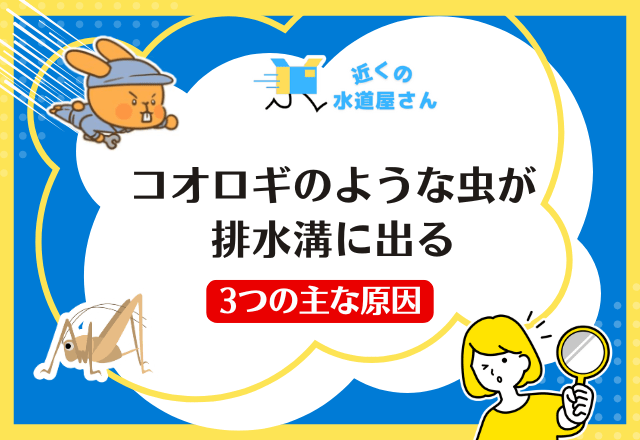
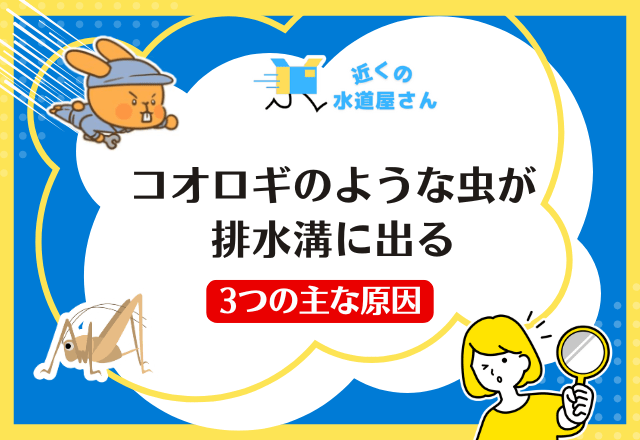
夜、洗面所で黒い虫がピョンと跳ねた——。
よく見るとコオロギのような姿。けれど、屋外ならまだしも、
「なぜ家の排水口からコオロギが?」と驚く方は多いでしょう。
実は、これは排水設備の異常サインである可能性があります。
排水口には“トラップ”という構造があり、常に水がたまって下水との間を、下水から虫や臭いが上がらないよう遮断しています。
しかし、長期間使っていない洗面台や浴槽では、水が蒸発してトラップが空になり、その隙間から下水の虫が上がってきます。
使用頻度の少ない洗面・浴室の排水口があれば確認してみましょう。
乾いている・臭う場合は封水が切れている可能性大です。



排水トラップの水がなくなる原因と対策については、以下の記事でも詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらもご一読ください。


配管のつなぎ目や、床下を通る排水管のまわりにできたすき間も侵入経路になります。
経年劣化や施工不良により、わずか数ミリの隙間からでも虫が侵入することがあります。
湿気が多く、光が届かない環境は虫にとって最適な棲みかです。



「水漏れしていないのに虫が出る」という場合は、
この配管まわりのすき間を疑うとよいでしょう。
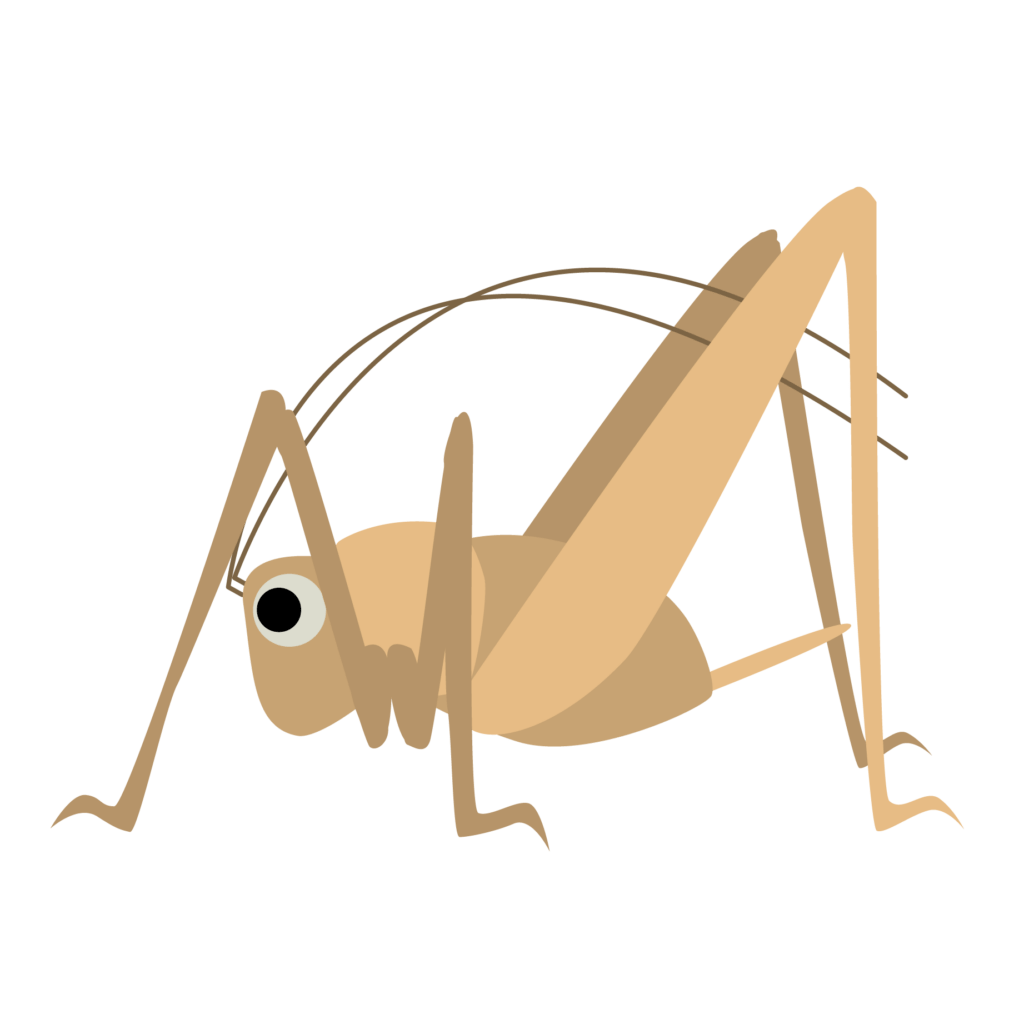
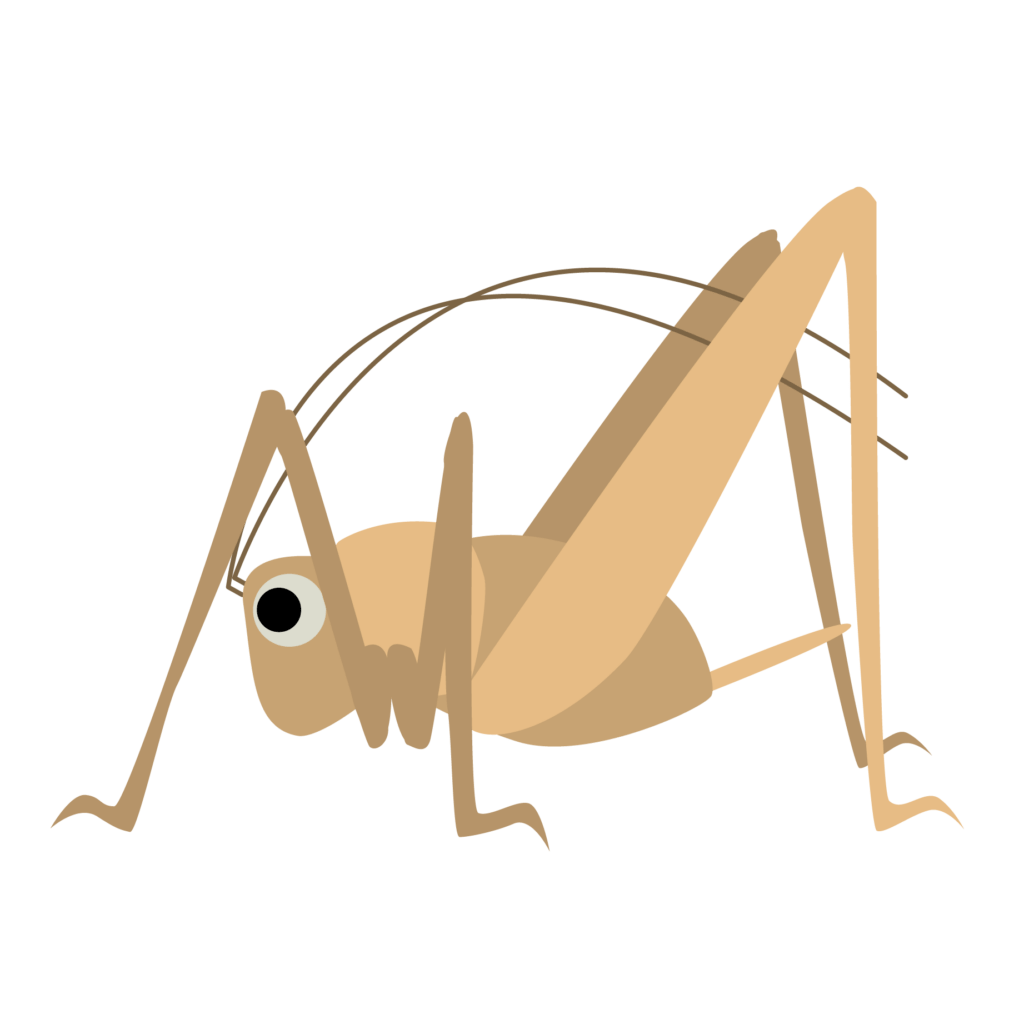
排水口で見かける“コオロギそっくりの虫”の多くは、実はカマドウマ(別名:便所コオロギ)です。
音を立てず、長い脚で跳ねる動きが特徴。
夜行性で湿気と暗さを好み、浴室・脱衣所・トイレなどに潜みます。
一見コオロギに見えますが、屋外の草むらではなく屋内の水回りで繁殖する害虫です。
見分けがつかない場合でも、対処法は同じく「湿気を減らす」「侵入口を塞ぐ」が基本です。
排水口や湿った場所でよく見かける「カマドウマ」は、別名「コオロギモドキ」とも呼ばれ、コオロギに似た見た目をしていますが、実はまったく違う種類の虫です。
直接的な咬みつきや毒はありません。
ただし、見た目の不快感に加えて、排水まわりの汚れを運んだり、他の害虫を呼び寄せたりすることがあります。
衛生面の悪化や臭いの原因にもなるため、“害は少ないが放置はNG”と覚えておきましょう。



実際に調べてみると害虫というより、害虫を食べる「益虫」とされる虫です。しかしながら家に湧くのは衛生的によくありませんね。



「水回りに発生しやすい虫」については、以下の記事でも詳しくまとめているで!興味がある人はぜひこっちもチェックしてみてな。




排水口から虫が上がるのは、構造上の問題が潜んでいるサインです。
放置すると次のようなリスクにつながります。
虫が繁殖する環境は、汚れやぬめりがたまりやすく、細菌やカビの温床になります。これにより悪臭が発生し、室内環境が悪化します。
虫のフンや死骸、微細なホコリはアレルギーや喘息などの健康被害を引き起こすことがあります。特に子どもや高齢者がいる家庭では注意が必要です。
雑菌が繁殖した排水口から、キッチン周りに細菌が拡散することで食中毒の原因となる恐れがあります。
虫の活動や汚れの蓄積が配管内での詰まりを加速させ、水の流れを悪くします。
放置すると排水不良や漏水の原因にもなります。
配管の隙間から虫が床下や壁の内部に侵入し、木材の腐敗やカビの発生を促進します。これにより建物の耐久性が低下する恐れがあります。
虫トラブルを放置すると、被害範囲が広がり修理や補修の費用が高額になることが多いため、早期対応が経済的にも重要です。



「たかが虫」と思って放置すると、後々の修理コストや健康面のトラブルリスクが大きくなる恐れがあるで!


ネット上やSNSでは、「家の中からコオロギのような鳴き声が聞こえてきた」「排水口を開けたら虫がいて驚いた」という体験談が多く寄せられています。
ここでは、いくつかの実際の事例と、それに対する専門家のコメントを交えて紹介します。
「ある夜、家の中からコオロギのような鳴き声が聞こえてきて気になり、お風呂の排水口を開けてみたら小さな虫が何匹かいました。慌てて虫取り網で捕まえて外に逃がしましたが、まさか排水口にコオロギがいるとは思わず驚きました。」
排水口の封水(トラップ)がしっかり機能していないと、コオロギやカマドウマが侵入しやすくなります。
封水の蒸発や配管の劣化は、虫の侵入経路になるため定期的なチェックが必要です。
「洗面台で黒い虫を見かけて、最初はゴキブリかと焦りました。でもよく見ると足が長くて、どうやらコオロギの仲間かもしれません。どこから入ってきたのか不安で…」
コオロギやカマドウマはゴキブリと違い、攻撃性はほとんどありませんが、湿気の多い排水口まわりを好みます。
建物の隙間や配管の接合部から侵入してくることが多いので、隙間をふさぐことが重要です。
北海道の築40年の古い家に住んでいますが、浴室の排水口にカマドウマが大量発生。専門業者に相談したら、排水口の掃除の仕方や封水の管理、床下の点検も勧められました。おかげで徐々に虫の数が減っています。
古い建物は排水設備の老朽化が進み、虫の侵入や繁殖に適した環境になりやすいです。
特に北海道のような寒冷地では封水が凍結や蒸発しやすいため、専門家による点検と適切なメンテナンスが必要です。



これらの実例は、排水口まわりの虫トラブルが決して珍しいものではないことを示しています。虫の侵入経路や繁殖環境を理解し、早めに適切な対策を行うことが快適な住環境を保つポイントです。


カマドウマは湿気が多く、暗くて暖かい場所を好みます。
具体的にどのような場所に湧きやすいのかを知っておくと、効果的な対策につながります。
湿気が多く、温度も比較的安定しているため、カマドウマにとって理想的な生息環境です。
特に、封水が乾燥していたり、ぬめりや汚れが溜まっている排水口は、餌となる微生物や汚れが多く、繁殖が活発になります。
湿気がこもりやすく、暗いため、カマドウマが隠れやすい場所です。
床下や壁の隙間、配管の接合部の隙間から侵入し、そこで繁殖することがあります。
換気が不十分な地下室や物置は湿度が高く、カマドウマが好む環境です。
古い建物や戸建て住宅の基礎部分にも多く発生します。
外の排水桝や雨どいの下など、湿った土壌や落ち葉がたまる場所にも湧くことがあります。
そこから家の中へ侵入してくるケースも少なくありません。
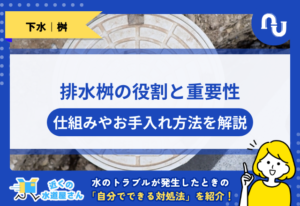
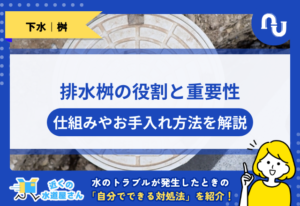


排水口のコオロギやカマドウマなどの虫トラブルは、日々のちょっとした工夫で大幅に減らすことが可能です。
ここでは、すぐに実践できる掃除のポイントや封水の管理、湿気対策など、自宅で手軽にできる具体的な対策方法を詳しく紹介します。
排水口に残った石けんカスや髪の毛、油汚れは虫のエサになります。
月に数回、ブラシでカバーを外して洗い、漂白剤または重曹+クエン酸でぬめりを除去しましょう。
掃除後は水をしっかり流し、封水を維持することが大切です。
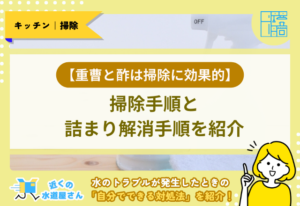
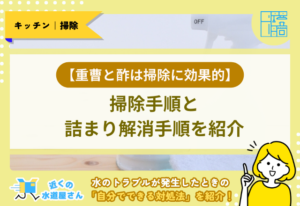
長期間使っていない洗面や浴室は、週1回程度でコップ一杯の水を流すようにしましょう。
もしトラップが古く、封水が切れやすい場合は、水道業者に点検を依頼すると安心です。
排水ホースと壁の穴の間、床下点検口、浴室の排水まわりなど、すき間を見つけたら防虫パテやゴムパッキンで塞ぎましょう。
ホームセンターでも手軽に入手できます。
コオロギ型の虫は湿気を好むため、乾燥環境を作ることが最大の予防になります。
湿気を減らすことで、虫だけでなくカビやダニの防止にもつながります。



湿気がこもりやすい浴室では換気が必須。
お風呂の換気扇が回らないなど、不具合が気になるときは以下の記事が参考になりますよ。


薬剤や忌避剤を使うときは、以下の点に注意しましょう。
ただし、これらは一時的な対処法にすぎません。
根本原因が配管や封水不良にある場合は、再発する可能性が高いです。
カマドウマに対して市販の殺虫剤を使用する場合、一定の効果は期待できますが、根本的な解決にはなりません。
理由は以下の通りです。
カマドウマを見かけたら、殺虫剤に頼るよりもまず、排水口のぬめり掃除や封水の管理、湿気対策を徹底することが重要です。
それでも改善しない場合は、排水管の隙間や配管の劣化を専門業者に調査してもらうことをおすすめします。
虫取り網で捕まえて逃がすのは、一時的に虫を減らす手段としては有効ですが、根本的な虫の発生原因を解消することが重要です。
掃除や封水の管理、湿気対策をしっかり行い、必要に応じて専門業者に点検・修理を依頼することで、長期的な虫トラブルの解決につながります。
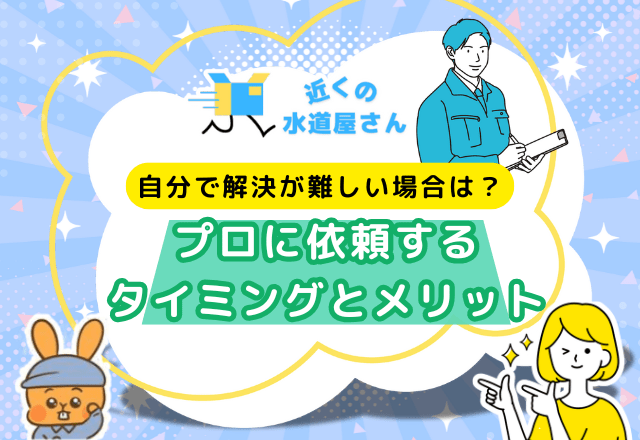
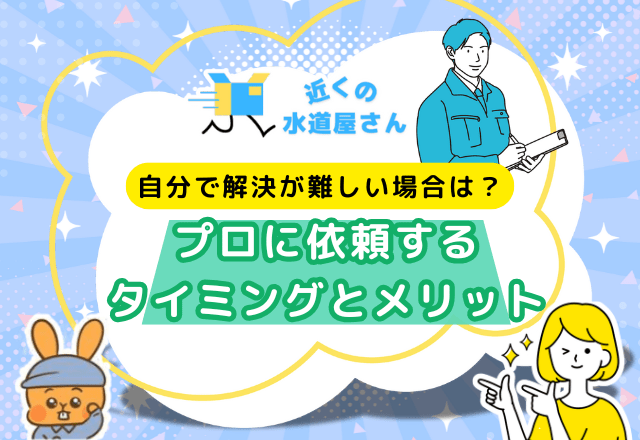
自分での掃除や対策を試しても、排水口の虫トラブルが解消しない場合は、専門的な調査と修理が必要になることがあります。
ここでは、専門業者がどのような対応をしてくれるのか、また信頼できる業者を選ぶポイントについて詳しく解説します。


特に築年数が10年以上経っている建物では、配管の劣化や施工ズレが原因で虫が侵入するケースも珍しくありません。
「掃除しても毎回出る」「複数箇所から虫が上がる」という場合は、早めに水道修理業者へ相談しましょう。
排水口の虫トラブルを根本的に解決するためには、信頼できる水道修理業者の力を借りることが大切です。
しかし、数多くある業者の中から安心して任せられるところを見極めるのは簡単ではありません。
ここでは、後悔しないために押さえておきたい業者選びのポイントをわかりやすく解説します。
単なる水漏れ対応だけでなく、「配管の虫対策」経験があるか確認。
出張費・作業費・部品代がはっきり記載されているかをチェック。
複数社を比べることで、料金相場や対応スピードが分かります。



水道業者を選ぶときは、住んでいる自治体の水道局指定工事店の中から選ぶこと!まずは無料見積もり&相談に対応している業者を選ぶといいで!



本サイトでは、日本各地の水道局指定業者を掲載しています。
業者選びに迷った際はぜひ活用してくださいね。





排水口からコオロギが出るトラブルについてよくあるQ&Aをまとめました!



気になる項目があったらぜひチェックしてみてな!
排水口から出てきた虫、本当に「コオロギ」なんですか?
多くの場合、見た目がコオロギに似ている「カマドウマ(通称:便所コオロギ)」です。
体色が黒く、長い脚でピョンと跳ねるため混同されがちですが、
本物のコオロギは外で生活し、屋内の排水口に現れることはほとんどありません。
便所コオロギは湿気の多い浴室・洗面所・床下を好み、排水管の隙間から侵入します。
どうして排水口から虫が上がってくるんですか?
排水管には「封水(トラップ)」という水の栓があります。
これが乾いていたり、配管に隙間があったりすると、下水側から空気と一緒に虫が上がってきます。
特に長期間使っていない洗面台や浴槽は、封水が蒸発していることが多いです。
定期的に水を流すだけでも予防になります。
一匹だけなら放っておいても大丈夫ですか?
一匹でも油断は禁物です。
排水口や床下に卵が残っている可能性があり、
条件が整うと短期間で繁殖することもあります。
見つけたらすぐに掃除・除湿を行い、侵入経路を塞ぎましょう。
繰り返し見かけるようなら、配管の不具合が疑われるため業者に相談してください。
虫が出やすい季節はいつ?
春から秋にかけての湿度が高い時期(5〜10月)に多く発生します。
気温が20℃を超えると繁殖が活発になり、特に梅雨〜夏場は排水口のぬめりが虫の温床になりやすいです。
冬でも暖房による湿気で発生する場合があるため、季節を問わず定期的なメンテナンスをおすすめします。
マンションやアパートだと、自分だけ掃除しても意味ありますか?
部分的には効果がありますが、建物全体の配管構造が関係する場合もあります。
同じ棟で他の部屋が使っていない排水管があると、そこから虫が上がってくることも。
管理会社やオーナーに相談し、共用部の配管清掃や点検を依頼すると安心です。
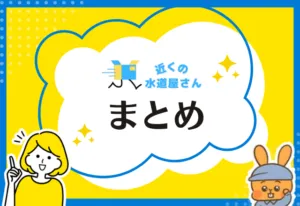
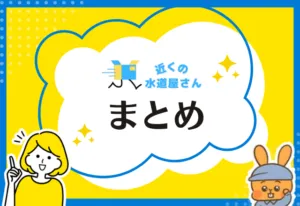
排水口や配管からコオロギやカマドウマなどの虫が発生する原因は、主に封水(トラップ)の機能不全や配管の隙間、そして湿気と汚れが生む環境にあります。
放置すると、衛生面の悪化や建物の構造被害につながるリスクが高まるため、早めの対策が大切です。
まずは、定期的な掃除や封水の管理、湿気対策をしっかり行い、排水口まわりを清潔に保つことが効果的。市販の駆除剤も使えますが、根本的な解決には環境改善が不可欠です。
それでも改善しない場合や配管の劣化が疑われる場合は、専門の水道修理業者に点検・修理を依頼しましょう。信頼できる業者選びは、口コミや実績、資格の有無を参考にすることが重要です。