
近くの水道屋さんが見つかる
ポータルサイト
おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載



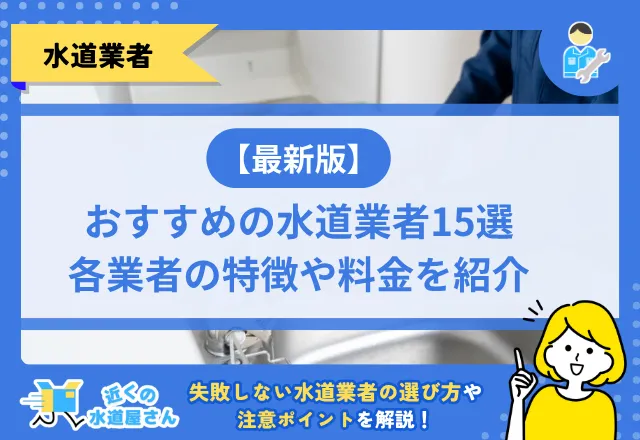
毎週掃除しているのに、なぜか落ちないお風呂の黒カビ。
「漂白剤を使っても薄くなるだけ」「何度やっても同じ場所にまた生える」――そんな経験はありませんか?
実はその“取れないカビ”、掃除方法が間違っている可能性があります。また、カビの種類によっては、家庭用の洗剤だけでは完全に除去できないことも。
 ビアス
ビアスそこで本記事では、初心者でもお風呂にこびりつく頑固なカビを簡単に落とせる方法、カビの繁殖を防ぐ対策について紹介します。



カビを落とすのに効果的な薬剤や、道具についても紹介していくで!
お風呂のカビ汚れに困っている人はぜひ最後まで見たってや!


「こすっても落ちない」「何度掃除しても同じ場所にまたカビが…」そんな経験がある方は少なくありません。
実は、お風呂のカビが落ちないのには明確な原因があります。この章では、見落としがちな3つのポイントを解説します。


お風呂に発生するカビの中でも、特にしつこいのが「黒カビ(クラドスポリウム)」です。見た目は黒い点や斑点状で、ゴムパッキンやタイルの目地に多く発生します。
黒カビは表面だけでなく、素材の奥に根(菌糸)を張るのが特徴です。
これが、いくら表面をこすっても「また同じ場所に現れる」原因です。
天井やタイルの目地、排水口の他ドアや窓のゴムパッキンにまで強く根付きます。
さらに黒カビはアレルギー症状や皮膚炎、免疫力の低下など人体の健康に悪影響を及ぼすのも特徴です。
浴室を含む全ての水廻り環境だけでなく、湿度が高い環境なら室内のカーテンや壁、天井にも発生します。
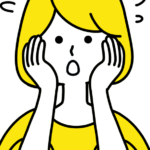
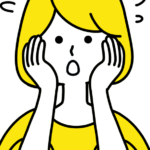
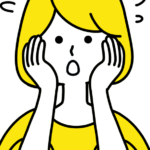
なんといっても厄介なのが、表面をこすり落とせたと思っても根本が残っていると何度も再発することです。
市販のカビ取り剤は、表面の菌を一時的に除去するものが多く、奥深く入り込んだ菌糸までは届かないケースも。
特に、ゴム素材や古いシーリング部分は薬剤の浸透力が弱まり、カビの根を完全に除去できません。
カビは、以下の3つの条件が揃うことで爆発的に繁殖します。
お風呂はこの三要素が常に揃っているため、掃除しても環境が改善されていなければ、カビは再発しやすいのです。
環境改善をせずに掃除だけしても、カビの原因はそのまま残っているため、「何度やっても取れない→またカビが生える」というループに陥ってしまいます。



めったにはないケースやけれど、環境や状況によってはお風呂場にきのこが生えてくることもあるで!



お風呂場にきのこが生える原因と対処法については、以下の記事で詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらも参考にしてみてくださいね!




お風呂のカビは見た目が不快なだけでなく、放置すると健康にも悪影響を及ぼすことがあります。
しかし、ただ闇雲に掃除を繰り返すだけでは、カビを根本から取り除くことはできません。
ここでは、市販のカビ取り剤を効果的に使い、再発を防ぐための正しい手順と注意点を詳しく解説します。
この方法を守れば、カビの根にもしっかりアプローチでき、清潔なお風呂を長くキープできますよ。
それでは、一つひとつのステップを見ていきましょう。
カビが取れないからといって、間違った方法で掃除を繰り返すと、かえってカビを悪化させることがあります。以下のような方法は要注意です。
を入れてこすっても、カビの「根」は落ちません。
むしろ、ゴムパッキンや目地の素材を傷つけてしまい、傷口からさらにカビが浸透しやすくなるリスクがあります。
重曹は安全で万能なイメージがありますが、カビの漂白・殺菌力は弱めです。
また、酸性洗剤(トイレ用洗剤など)とカビ取り剤(塩素系)を混ぜて使うと有毒ガスが発生する危険性があります。絶対に混ぜないでください。
塩素系のカビ取り剤は時間をかけて成分が浸透し、殺菌・漂白を行うものです。放置時間が短すぎると効果が発揮されず、「効かなかった」という結果になります。
市販のカビ取り剤でも、正しい方法で使えば根の深いカビにも効果があります。
ポイントは以下の3つです。
水分が残っていると薬剤が薄まり、効果が弱くなります。掃除前に対象部分をしっかり乾かすことで、薬剤がしっかり浸透します。
カビ取り剤の成分(次亜塩素酸ナトリウムなど)は20〜30℃で活性化します。冬場や浴室が冷えているときは、
などで温度を上げてから使うと、効果が格段にアップします。
取れないカビほど、時間をかけてしっかり漂白・殺菌する必要があります。説明書に従って、十分な時間放置しましょう。
ここでは、初めての方でも実践しやすい「カビ取りの4ステップ」を紹介します。
順を追って作業することで、洗剤の効果を最大限に引き出し、カビを根本から除去することができます。
まずはお風呂場に水分がない状態にする必要があります。
水滴は雑巾で拭き取り、お風呂場内の湿気を取るために10分程度換気しましょう。
また、掃除をおこなう際には、天井に直接シャワーを当てないようにしましょう。カビは水やお湯で洗い流しただけでは落ちることはなく、水滴は下へ垂れ流れてきます。
届きにくい天井のカビとりには、柄の長いクイックルワイパー等を用いることで対処しましょう。
次にカビ取り洗剤をカビに直接散布します。
カビ取り洗剤が垂れてしまっても大丈夫なようになるべく多く散布しておくと良いでしょう。
散布した部分にはラップをかけます。これによってより洗剤がカビに確実に届くようになり、仕上がりもキレイになります。
その後、ラップをしたまま20分ほど放置します。この時は換気せず、お風呂場を密閉させておきましょう。



ゴムパッキン等に強く根付いたカビには、塩素系漂白剤+片栗粉を混ぜたペーストが効果的やで!またはジェルタイプのカビキラーPROを使用することもおすすめや。



片栗粉は中性なので塩素系漂白剤と混ぜても問題はありません。また、ハイターが自宅にあるのなら塩素系漂白剤を購入せずとも代用が可能です。
放置することで、こびりついたカビが浮き出てきます。
歯ブラシを使ってこすって、残っているカビを掃除しましょう。
あとはカビ取り洗剤を水で洗い流しましょう。
カビや汚れが残っている場合は、歯ブラシで強くこすって掃除します。雑巾で拭くのも効果的です。



根強く残っている黒カビにはもう一度同じ工程を試してみてや!
それでも取れない場合は、以下のような「ひと工夫」を加えることで、頑固な黒カビにも対応できます。
重曹は研磨効果+密着性があるため、カビ取り剤の上から重曹を重ねることで、薬剤がより長く留まりやすくなります。
このときも、換気と手袋・マスク着用は必須です。
カビ取り剤を塗布した上に食品用ラップをピッタリ貼りつけて密閉します。これにより、
というメリットがあり、特にゴムパッキンや目地のカビに有効です。
見落としがちな天井の黒カビも、繁殖源の一つです。
市販の「お風呂天井ワイパー」や伸縮ポール付きの掃除グッズを使い、カビ取り剤を染み込ませたシートで拭き掃除すると安全に清掃できます。
お風呂(浴室)のカビ掃除には、「塩素系漂白剤」「酸素系漂白剤」を使用します。
酸素系漂白剤は使用上において安全な洗剤ですが、除菌・漂白効果はカビの根元から殺菌できる塩素系漂白剤と比べるとやや劣ります。
反対に塩素系漂白剤は臭いや成分が強い為、取り扱いの際は決して触らない・吸い込まないといった注意が必要です。
また、酸性の薬品とは混ぜない・お湯で流さないといったことも徹底して注意してください。
| 洗剤の種類 | 殺菌効果・刺激 | 安全性 | 有名な製品 |
|---|---|---|---|
| 塩素系漂白剤 | ・カビハイター ・カビキラー | ||
| 酸素系漂白剤 | ・オキシクリーン ・ワイドハイター |



同居者に体の弱い人・ご高齢者・子供・嗅覚の強いペットがいる場合は、酸素系漂白剤がおすすめやで!



根を張っているほどに頑固な黒カビでなければ、酸素系漂白剤で十分に落とせるはずです!浴室が大理石素材の場合も酸素系漂白剤を使用するようにしましょう。
以下では、カビ取りに強力な効果を発揮できる洗剤についてご紹介いたします。
カビキラーは言わずと知れたカビ対策の王道です。
ゴムパッキンの間に入り込んだカビにも効果抜群の商品です。一度掃除すれば30日間はしなくても効果が持続します。
黒カビにはもちろん、お風呂場のピンク色のぬめりにも対応しています。
黒カビの表面は簡単に落とせますが、問題なのは根本です。
カビハイターはしつこい黒カビを根本から撃退してくれます。密着泡によって壁のカビも泡が垂れずにしっかり落としてくれます。
| ラップ | カビ取り洗剤を使用した後に、散布箇所にラップをかける |
|---|---|
| 歯ブラシ | カビをこする |
| 雑巾 | ピカピカに磨きたいのであれば用意 |
ラップはキッチンペーパーで代用することも可能です。歯ブラシはいらなくなったものを用意すれば大丈夫です。
カビ取り洗剤を流す前に、歯ブラシでカビをこすることでキレイになります。
雑巾はなくても大丈夫ですが、ピカピカに磨きたいのであれば用意しておきましょう。
カビ取り洗剤を流したあと、雑巾で拭けばよりキレイになります。
お風呂のカビ掃除に薬剤を使用する際には、いくつか注意点があります。
カビ取り掃除は誰でもできる作業ですが、間違ったやり方を取ってしまうと健康状態に影響を及ぼす恐れがあるため、必ず目を通すようにしてください。
お風呂のカビ掃除をおこなう際には薬剤を使用しますので、必ず喚起を回しながら作業をおこなうようにしましょう。
お風呂のカビ取り掃除をおこなう前日から換気扇を回して、掃除の際には完全に乾いた状態が望ましいです。
カビ取りの際に限らず、薬剤を使用する際には混ぜ合わせてはいけないものに注意が必要です。
| 酸素系漂白剤 | 塩素系漂白剤 | 中性洗剤 | |
|---|---|---|---|
| 塩素系漂白剤 | – | ||
| 酸素系漂白剤 | ‐ | ||
| 中性洗剤 | – |
また、お湯で洗い流す際には40℃~60℃程度の温度に設定しましょう。熱湯は排水管を傷めるだけでなく、漂白がうまく作用されません。
さらに塩素系漂白剤は急速に塩素ガスを発生させてしまうので、熱湯は決して流さないようにしてください。
このほかにも、薬剤によっては材質に影響を与えてしまう・一部の汚れにはうまく作用できないことがあるので、使用の際は製品に記されている注意書きを必ず確認しておきましょう。
お風呂(浴室)のカビ取りに使用する道具の説明と重複しますが、薬剤を使用する際には安全のためにゴム手袋・ゴーグルを着用しましょう。
万が一薬剤が素肌に付着した場合は、早急に多量の水で洗い流します。その後異変等があればお近くの診療所で診療を受けるようにしてください。
塩素系漂白剤は強力な漂白効果があることから、長時間放追することによってお風呂の設備の劣化・変色を引き起こす恐れがあります。
浴室のお風呂や窓部分のゴムパッキンなども硬化する、脆くなってしまうなど劣化を早める要因となってしまいます。
また、長時間放置することによって刺激臭から体調を崩す恐れもあるため、必ず既定の置き時間を守って洗い流すことが大切です。



漬け置けば漬け置く程に汚れが落ちると勘違いされやすいけれど、メーカーが定めている規定時間を守ることが重要やで!



台所の食器洗いの漬け置き洗いも同様です。長く放置すればするほどかえって最近が繁殖しやすい状態となってしまいます。食中毒のリスク等もあることから2時間以上の漬け置きは推奨はされていません
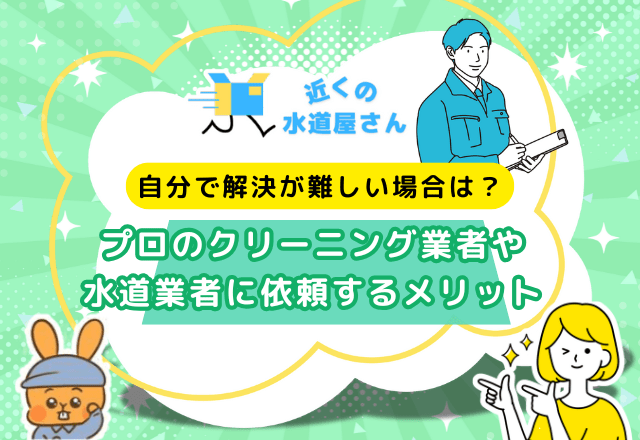
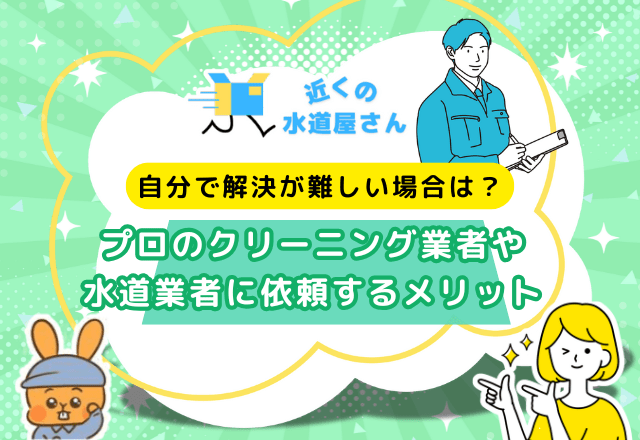
お風呂のカビが自分でどうしても落とせないと感じたら、無理をせずプロの手を借りるのも賢い選択です。
ここでは、自力で対処できるカビとそうでないカビの見極め方、業者の費用相場や選び方、賃貸物件でのカビ問題について詳しく解説します。
カビの状態によって、自分で掃除できる範囲とプロに依頼したほうが良いケースがあります。
無理に自分で取り除こうとすると、カビを広げたり健康を害する恐れもあるため、適切に判断しましょう。
プロのハウスクリーニング業者に依頼する場合の費用や選び方のポイントは以下の通りです。
浴室カビ除去単体の料金は、1万円~3万円程度が一般的です。
カビの範囲や状態によって変動し、広範囲の場合は料金が高くなる傾向にあります。
定期的な浴室クリーニング(カビ予防含む)をセットにすると、割引やメンテナンス効果も期待できます。
施工事例やお客様の声が公開されているか
単なる掃除だけでなく予防策も教えてくれる業者が安心
再発時の保証や再対応があるかどうか
追加料金やオプション料金がわかりやすいか
お風呂のカビは基本的に掃除やクリーニングで対処できますが、カビの原因が水回りの設備や配管のトラブルに起因している場合は、水道業者への相談が必要です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
壁内部や床下の漏水は湿度を高め、カビの温床になります。
漏水により常に湿った状態が続き、カビが発生しやすくなります。
排水不良は湿気をため込み、カビが広がる原因となります。
見えない箇所の水漏れは気づきにくく、専門業者による点検・修理が必要です。
換気扇の配線や換気ダクトの詰まりなども水道業者や設備業者と連携して点検が必要です。
賃貸住宅に住んでいる場合、お風呂のカビはトラブルの原因になりやすいため、特に注意が必要です。
特にカビによる汚損は「借主の過失」と判断されることもあり、敷金からクリーニング費用が差し引かれるケースがあります。
入居前からのカビは借主の責任外のため、写真や報告書で証拠を残しておくことが重要です。



もし自力で落とせないカビがある場合は、早めに大家や管理会社に相談するのもトラブル回避に効果的です。
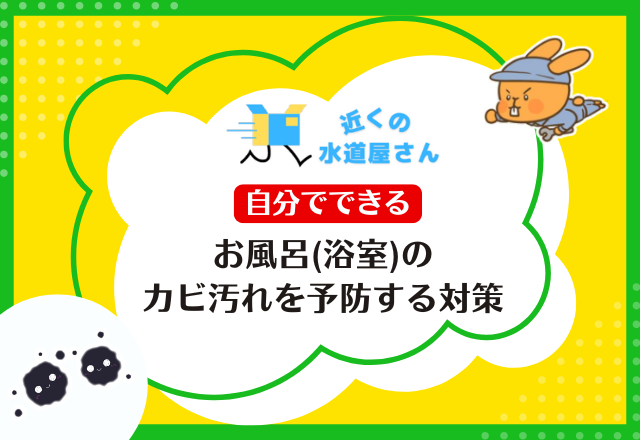
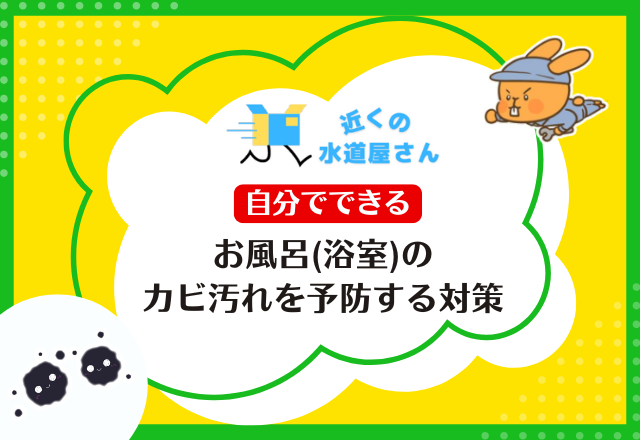
お風呂にカビが根付かないように大切なのは普段からの予防対策です。
カビが嫌うのは【50℃以上の熱】【乾燥】【薬剤】の3つとされています。ウイルスと同じく冷凍状態になっても生存はしますが、50℃以上の熱によって死滅します。
ただし、排水管の耐熱温度は60~70℃程度とされていますので、排水口や排水管を傷めないためにもお湯を流すときは温度に注意しましょう。
| 熱 | 50℃以上のお湯を流す |
|---|---|
| 乾燥 | 換気扇を常に回す |
| 薬剤 | カビを分解・殺菌できる |
次にまとめることは、日頃からできることですので、ぜひやってみてきください。
カビは湿度が高いところで繁殖します。
湿度が約60%以上だと、カビが活動できる湿度ですので、お風呂場はなるべく換気をしておくとカビ予防になります。
お風呂に入った後は換気をする、使っていなくてもこまめに換気をするなどして気を付けましょう。
換気扇を回して置く時間は、入浴後3時間程度が望ましいとされています。また、入浴時以外なら常に換気扇を回した状態にしておいても問題はありません。



換気扇はつけっぱなしでもそれほど電気料金が高くないで!
ただし、換気扇に汚れが溜まっている・異音がする・異臭がする等のサインが起きているときは要注意や!



お風呂の換気扇が回らない・故障のサインについては以下の記事で詳しくまとめています。気になる方はぜひこちらも参考にしてみてくださいね!


カビはお風呂(浴室)の壁や床、天井だけでなくシャンプーやコンディショナー、ボディソープ等の底部分がぬめっていることでも発生します。
できる対策としては、上記のボトルはお風呂の床に置かないということです。
浮かせる収納を取り入れる等、しっかり水切りできるような体制にしておきましょう。
カビは熱に弱いので、50~60℃程度のお湯を定期的に流すことも対策となります。
お湯をかけた後は冷水シャワーで浴室内の温度を下げ、その後は換気扇を回しておきましょう。
銀イオン成分による煙タイプのカビ予防剤です。
塩素不使用かつ、煙タイプなので手間もかからない点が特徴です。
1~2ヵ月に1回使うだけでカビの予防になります。





お風呂のカビ汚れに関してよくあるQ&Aをまとめました!



時間に余裕のある人はぜひ最後まで見たってや!
お風呂のカビ除去・クリーニングはどこに依頼すれば良いですか?
カビ取り業者・ハウスクリーニング業者に依頼することができます。
浴室の目視で確認しづらい部分や、届かない部分のカビ汚れまで徹底的に除去したい場合は専門業者に依頼するのが得策です。
お風呂のカビ対策として入浴中に換気扇を回しても問題ありませんか?
入浴中に換気扇を回すと、結露が発生しやすい状態となることから推奨されていません。
浴室の天井に結露が発生することでかえってカビが発生しやすい状態となってしまいますので、入浴中に換気扇を回すことは控えておきましょう。
賃貸物件を退去するときにお風呂のカビ汚れは指摘されますか?
清掃等の対策を取っておらず、あまりに状態が酷い場合は原状回復の義務として費用を請求される可能性があります。
これはお風呂だけでなく、結露の放置などによって発生した壁のカビ汚れ等も同様です。
どれだけ対策をおこなっても建物の構造上でカビが発生しやすい物件であれば、大家さん・管理会社側が負担する必要があります。
このようなトラブルを避けるためにも、賃貸物件を探す際には湿度環境や責任の有無についてあらかじめ確認しておくと安心です。
カビ取りに重曹・クエン酸は使用できますか?
使用可能です。重曹とクエン酸が複合することで発砲する泡は汚れを浮かび上がらせる効果があります。
ただし、強く根を張るほどの頑固なカビには効果は期待できません。また、クエン酸は塩素系漂白剤と混ざると有害なガスを発生させます。
重曹とクエン酸を使用した直後に薬剤を使用しないように注意してください。
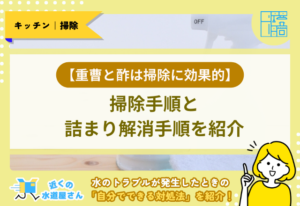
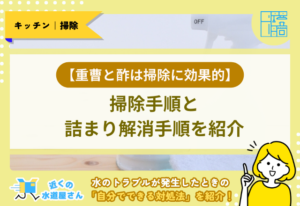
ロドトルラは人体に悪影響を及ぼすのでしょうか?
現在のところ、ロドトルラとは一般的に無害とされています。
しかしながら、免疫力が低下している人や特定の医療条件がある場合には、感染症を引き起こすことがあります。
つまり健康な人に対しては通常問題ありませんが、免疫抑制状態の方は注意が必要です。専門医の診断を受けることが重要です。
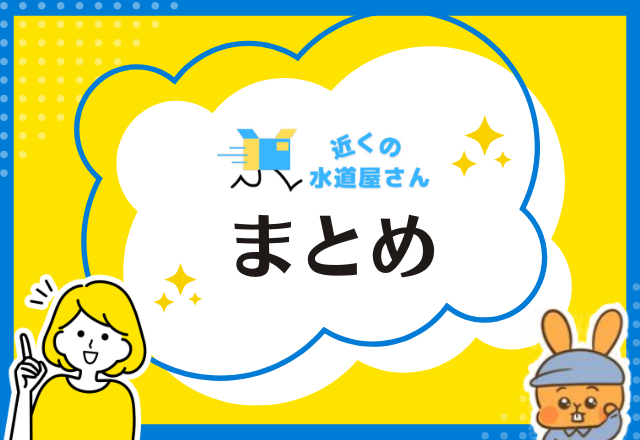
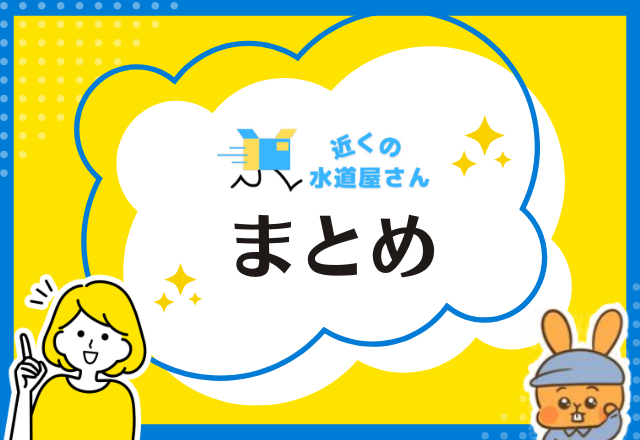
お風呂場のカビを落とす掃除方法を解説していきました。
カビは放っておくとより繁殖してしまうので、なるべく早く対処が必要です!
また、日頃からのカビ予防も重要になるので、ここで解説したことを参考に気を付けてみてください。