
近くの水道屋さんが見つかる
ポータルサイト
おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載



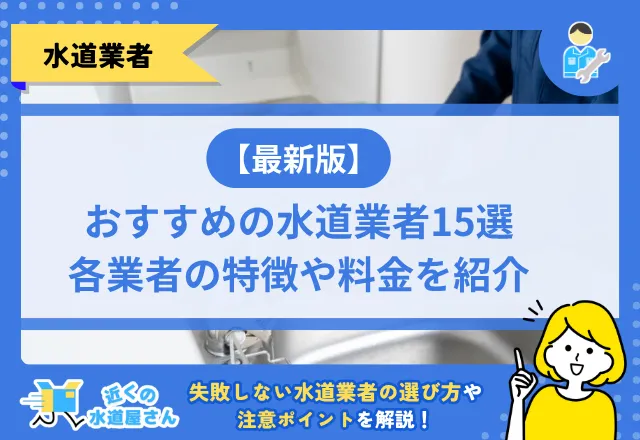
「排水口のヌルヌルがなかなか取れない」「掃除してもすぐに臭いが戻ってくる」
そんなお悩みを抱えていませんか?
実はその原因の多くは、“バイオフィルム”と呼ばれる膜状の汚れです。
一見ただのヌメリに見えるこの物質は、細菌やカビなどの微生物が作り出す強固な汚れの層であり、家庭用の洗剤やスポンジだけでは完全に取り除くのが難しいことも。
 ビアス
ビアス本記事では、バイオフォルムとは何か?排水口でなぜ発生するのかについて解説していきます。



家庭でできる効果的な除去・予防方法、業者相談の目安についても紹介するで!排水口のヌルヌル汚れに困っている人はぜひ最後まで見たってや。


排水口のヌメリや臭いの元となる「バイオフィルム」とは、一体どのようなものなのでしょうか?
このセクションでは、バイオフィルムの正体や、排水口で発生する理由についてわかりやすくご説明します。
バイオフィルムとは、細菌・真菌(カビ)・藻類などの微生物が、栄養分と水分のある環境で集まり、自ら分泌する粘着性の物質(多糖類)で作る膜のことです。
簡単に言えば、「微生物が共同生活しているヌルヌルの住処」のようなもの。
この膜は非常に粘着力が強く、一度排水口などに付着すると、スポンジで軽くこすった程度では完全に落とせません。
キッチンやお風呂の排水口にできる、あのヌルヌルとした汚れは典型的なバイオフィルムです。
水や食べかすなどの有機物が付着し、細菌が増殖して膜状の集合体を作っています。
歯の表面にできる白っぽいネバネバした汚れもバイオフィルムの一種。
口の中の細菌が唾液中の成分と結びついて形成され、虫歯や歯周病の原因になります。
浴室の壁やタイルの目地にできるぬめりもバイオフィルムです。
湿気と石けんカスが細菌やカビの温床となり、バイオフィルムを形成しています。


水槽の壁面や池の石などに付く緑色や茶色のヌメリもバイオフィルム。
藻類や細菌が集まって層を作っている状態です。
家庭の排水口は、バイオフィルムが発生しやすい代表的な場所です。
その理由は以下のとおりです。
そのため、定期的な掃除や除去を怠ると、見た目以上に深刻なトラブルに発展してしまう可能性があります。
バイオフィルムは細菌や微生物が集合して作る粘着性のある膜で、排水口やキッチン周りの湿った場所に形成されやすいです。
このバイオフィルムは、害虫にとっては格好の「住みか」や「餌場」になることがあります。
例えば、ゴキブリやハエなどの害虫は、バイオフィルム内に含まれる微生物や有機物を栄養源とし、繁殖の温床にします。
また、バイオフィルムが付着した場所は湿気が多く、害虫が隠れやすい環境を作り出すため、害虫の発生や定着を助長するのです。



バイオフィルムを放置すると害虫被害が増えるリスクが高まり、トイレや排水口の衛生状態悪化につながります。
害虫対策としても、バイオフィルムの除去と清掃は重要なポイントです。


排水口などにできるバイオフィルムは、多種多様な細菌やカビが集合して形成されています。
その中には、食中毒の原因となる病原菌が含まれている可能性もあります。
特にキッチンの排水口で発生したバイオフィルムは、食材のカスや油汚れが餌となり、細菌が繁殖しやすい環境です。
もしバイオフィルムがキッチン周りで放置されると、調理器具や食材に細菌が付着し、食中毒を引き起こす恐れがあります。また、
排水口の清掃が不十分だと、悪臭の原因になるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
日頃からこまめな掃除と除菌、そしてバイオフィルムの発生を防ぐ対策を行うことが、食中毒予防にもつながります。


排水管やトイレ内で発生する詰まりの原因は、トイレットペーパーや異物だけとは限りません。
実は、バイオフィルムという細菌や微生物が作り出す粘り気のある膜が、排水の流れを妨げていることが多いのです。
トイレの詰まりは、トイレットペーパーや異物が原因と考えられがちですが、実はバイオフィルムも詰まりの大きな原因の一つです。
トイレの排水管内には水分や有機物が豊富に存在し、細菌や微生物がバイオフィルムを形成しやすい環境となっています。
バイオフィルムは細菌が分泌する粘性のある物質で、排水管の内壁にしっかりと付着します。
これが徐々に蓄積し、ヌメリや汚れが固まっていくことで、排水の流れが悪くなり、最終的に詰まりを引き起こすことがあります。
さらに、バイオフィルムの粘着力によりトイレットペーパーや他の汚れが絡みつきやすくなり、詰まりが悪化しやすくなります。



最近トイレ詰まりの原因として増えているのが「バイオフィルム」による詰まりや。
原因としては水量が少ない節水トイレの普及が考えられるで。
トイレの排水管内にできるバイオフィルムは、形状としては黒っぽく、ぶよぶよとした粘着性のある膜状の汚れとして現れます。
このバイオフィルムは細菌や微生物が分泌する物質で形成され、排水の流れを妨げやすく、詰まりの原因となります。
また、糖尿病患者の場合、服用している薬の影響で排泄物の性状が変わりやすく、通常よりも排泄物が詰まりやすい傾向があります。



なお、糖尿病患者のトイレ詰まり対策については別記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひご参照ください。




排水口のバイオフィルムは、ただの「ヌルヌル」では済まないこともあります。
一見目立たない汚れですが、放置しておくと排水不良や悪臭、さらには健康面にも悪影響を与えることがあるため注意が必要です。
ここでは、バイオフィルムがもたらす代表的なトラブルについて詳しく解説します。
バイオフィルムは、微生物が活動する際に発生するガスや老廃物を閉じ込めやすい構造を持っています。
その結果、排水口からは次のような不快な臭いが発生するようになります。
この臭いは表面的な掃除ではなかなか取れず、排水口の奥まで根本的に対処する必要があります。
バイオフィルムは時間が経つとどんどん厚みを増し、排水口や配管の内側を覆ってしまうことがあります。
その結果、水の通り道が狭くなり、以下のような症状を引き起こします。
特に髪の毛や油分、石けんカスなどと絡まると詰まりやすくなります。
バイオフィルムの中では、目に見えない細菌やカビが集団で繁殖しています。
これらは空気中に飛散することもあり、浴室・キッチンなどでのカビ臭やアレルギーの原因になることもあります。
見た目では判断しにくい部分だからこそ、定期的な除去と清掃が重要です。
バイオフィルムは、外部からの刺激(薬剤・水流・ブラシなど)を弾く性質を持っており、放置時間が長いほど除去が困難になります。
そのため、いざ市販の洗剤を使っても、「臭いが取れない」「ヌルヌルが全然落ちない」といった結果になることも。
一見きれいになっているように見えても、奥にしっかり残っているケースが多いのです。
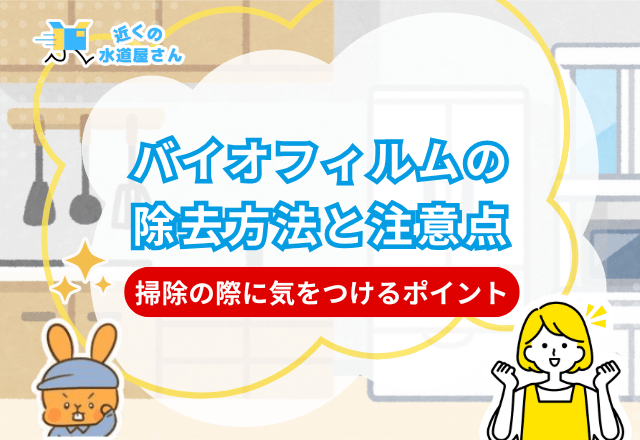
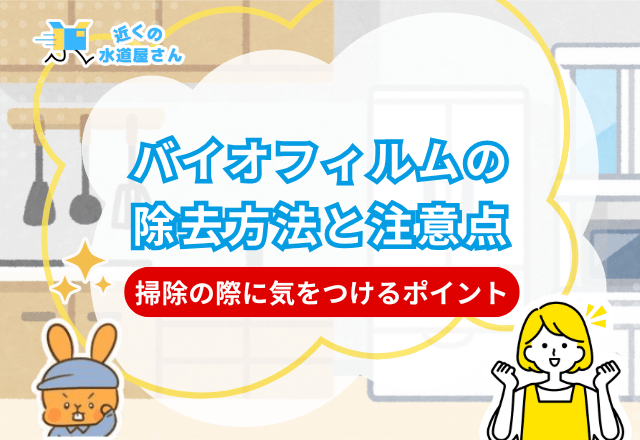
排水口にこびりついたバイオフィルムは、一般的なヌメリ汚れよりもしつこく落ちにくいのが特徴です。
このセクションでは、自宅でできるバイオフィルムの効果的な除去方法と、掃除の際に気をつけるべきポイントを解説します。
バイオフィルムを取り除くには、物理的な除去+洗浄剤の併用が効果的です。以下の手順を参考にしてください。
まずは、排水口まわりの部品を取り外して、バイオフィルムが付着している箇所を確認しましょう。
ヌメリ部分をこすることで、膜を壊して物理的に取り除くことができます。柔らかいブラシだと取り切れないので、少し硬めのブラシがおすすめです。
市販の排水口用のカビ取り剤や塩素系漂白剤を使うと、残った微生物の殺菌・分解に効果的です。
※使用時は換気・ゴム手袋の着用を忘れずに。
掃除後は40〜50℃程度のお湯でしっかり流すことで、洗剤残りや菌の再付着を防ぎます。



バイオフィルムは一度できると再発しやすいねん。
除去してもまたすぐに細菌が付着しやすいため、定期的なメンテナンスが欠かせへんで!
有毒ガス(塩素ガス)が発生し、命に関わる危険性があります。洗剤のラベルをよく確認し、絶対に混ぜないようにしましょう。
家庭用のブラシや洗剤では、排水管の奥に残ったバイオフィルムには届かない場合があります。流れが悪い、水が溜まる、臭いがすぐ戻るなどの症状があるときは、プロに相談したほうが安心です。
研磨力の強いブラシや強い洗剤を使いすぎると、排水トラップや配管パーツの劣化を早めてしまうことがあります。素材に応じた道具を選びましょう。


一度きれいにしても、バイオフィルムは1週間ほどで再び形成されることがあります。
清潔な状態を維持するために、以下のような習慣が有効です。



特に浴室やキッチンなど湿気の多い場所は、菌が繁殖しやすい環境のため、こまめな対策がポイントになります。
バイオフィルムは一度除去しても、再び発生しやすいため、日常的なケアが大切です。
ここでは、手軽に使えて効果的にバイオフィルムの再発を防ぐおすすめアイテムをご紹介します。これらを活用することで、排水口の清潔さを長期間キープできます。
コモライフの「バイオでぬめりドーン」は、排水口のヌメリや臭いの原因となるバイオフィルムを分解する洗浄剤です。
環境に優しいバイオ酵素を使っているので、排水管を傷めず安心して使えます。
定期的に使うことで、汚れの蓄積を防ぎ、長く清潔な状態を保てます。
排水口の臭いや詰まりが気になる方におすすめのアイテムです。
「さよならヌメリー」は天然成分100%の錠剤タイプの排水口クリーナーです。
化学薬品を使わず環境や排水管に優しいのが特徴。使い方は簡単で、週に1回排水口に投入するだけで、ヌメリや臭いの原因となるバイオフィルムをしっかり分解し予防します。
60錠入りで約1年分使えるためコスパも良好。
小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使える安全性も魅力です。
エムアイオージャパンの「ROEBIC K-97JD」は、6種類の天然バクテリアを使ったバイオ排水管クリーナーです。
化学薬品を使わず環境や排水管にも優しいため、安心して使えます。
使い方は簡単で、トイレに注いで水を流すだけ。初回は4日連続、その後は数回の使用で効果を維持できます。
悪臭対策にも効果的で、トイレや排水口を清潔に保ちたい方におすすめのアイテムです。
「除菌楽すてヘアキャッチャー」は、銅イオンの抗菌力で排水口のぬめりや嫌な臭いを抑える優れたヘアキャッチャーです。
髪の毛をまとめて効率的にキャッチし、排水口の詰まりを防止します。
銅素材は古くから抗菌効果が知られており、清潔な状態を長く保てるのが特徴です。
取り付けも簡単で、既存のヘアキャッチャーと交換するだけ。定期的なお手入れで効果が持続し、バスルームを快適に保ちたい方におすすめのアイテムです。
排水口の掃除後に氷や塩を使う方法は、一部で手軽なお手入れとして紹介されています。ここでは氷と塩、それぞれの効果や注意点について詳しく解説します。
氷は排水管の内壁に物理的な刺激を与え、付着したヌメリや汚れを剥がしやすくする効果があります。
また、氷の冷たさで一時的に細菌の活動を鈍らせることも期待できます。
ただし、排水管の形状によっては氷が詰まるリスクもあるため、多量に使うのは避けましょう。


塩には一定の抗菌作用があり、細菌の増殖を抑える効果が期待できます。
しかし、通常の掃除に使う量の塩ではバイオフィルムを完全に分解・除去することは難しいです。
さらに、塩分は排水管や設備に腐食のリスクを与えることがあるため、長期間や大量の使用は控えるのが賢明です。


排水口のバイオフィルムは汚れやぬめりが原因で発生しやすいため、定期的に温かいお湯を流すことが効果的です。
50~60℃程度のお湯を使うと、油汚れや汚れをやわらかくして流しやすくし、バイオフィルムの付着を防ぐことができます。
熱すぎるお湯は配管やゴムパッキンの劣化を早める可能性があるため、適度な温度での使用をおすすめします。
特にキッチンの排水口など、油汚れが気になる場所での活用が効果的です。
家庭でよく聞くバイオフィルム対策の一つに「アルミホイルを排水口に入れる」という方法があります。
これはアルミホイルが水に触れることで微量のアルミニウムイオンが溶け出し、細菌の繁殖を抑える可能性があるためです。
銅や銀の抗菌作用に似た効果が期待されることから、手軽な裏技として知られています。
しかし、実際にはアルミニウムの抗菌効果は銅や銀ほど強くなく、科学的な裏付けも限定的です。
そのため、アルミホイルだけに頼るのではなく、定期的な排水口の掃除や市販の除去剤、ヘアキャッチャーの使用と併用することが効果的です。


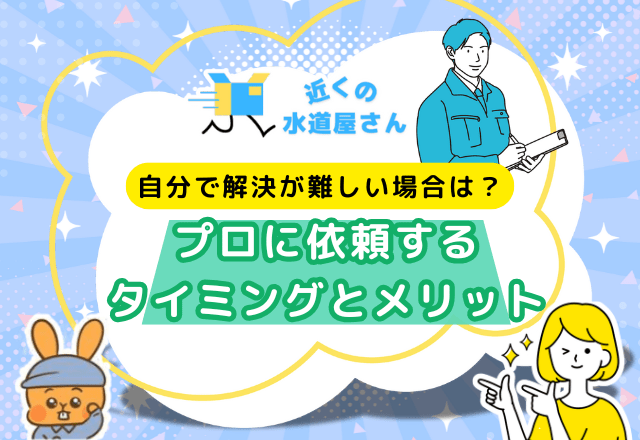
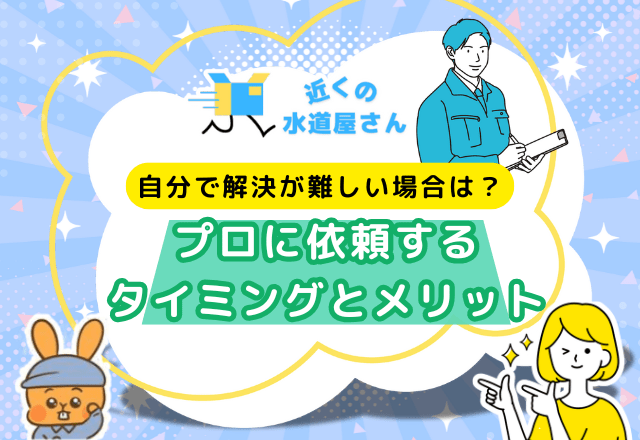
バイオフィルムは、軽度のものであれば家庭用洗剤やブラシで対処できますが、以下のようなケースでは専門業者の対応が必要になります。
特に築年数の経った住宅では、配管の老朽化や勾配不良など、バイオフィルムがつきやすい環境になっていることも多いため注意が必要です。
家庭での掃除では手が届かない範囲まで対応できるのが、プロの強みです。
水道業者に依頼した場合の料金は、以下が目安です。
| 作業内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 排水口の簡易洗浄 | 5,000〜8,000円程度 |
| 高圧洗浄による配管洗浄 | 10,000〜20,000円前後 |
| 詰まり除去・トラップ交換 | 15,000〜30,000円以上 |
※作業内容や地域によって異なるため、複数社の見積もり比較がおすすめです。
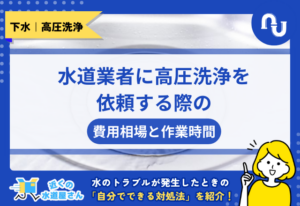
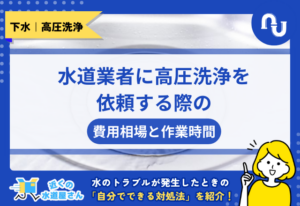



当サイトでは、日本全国各地の水道局指定業者を掲載しています。
業者選びに迷ったときはぜひ活用してくださいね。
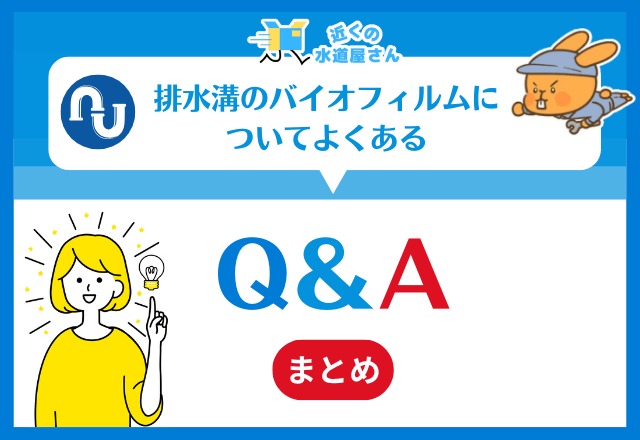
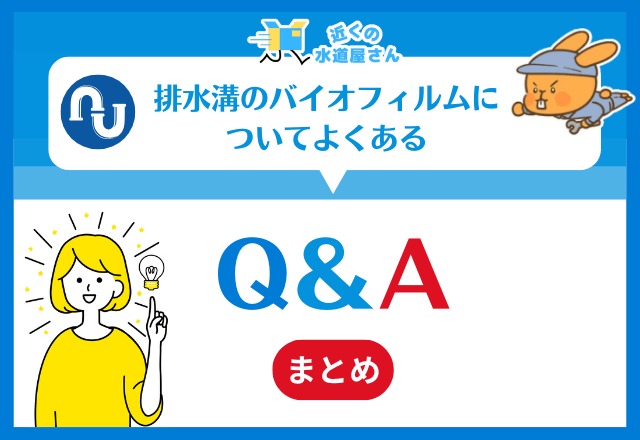



排水口のバイオフィルムについてよくあるQ&Aをまとめました!



気になる項目があったらぜひチェックしてみてな!
排水口のバイオフィルムを家庭で完全に除去できますか?
表面的なバイオフィルムであれば、ブラシ+塩素系洗剤などを使えば除去できます。ただし、排水管の奥深くに広がっている場合は、完全な除去が難しく、業者による高圧洗浄などが必要です。
バイオフィルムが健康に悪影響を与えることはありますか?
直接的に重大な健康被害は少ないですが、アレルギーや皮膚炎、喘息の悪化などの原因になることがあります。特に免疫力が弱い方は注意が必要です。
重曹や酢はバイオフィルム掃除に効果がありますか?
はい。重曹の研磨作用と酢の酸性成分がバイオフィルムを軟化・分解し、汚れを落としやすくします。環境にも優しい方法として人気です。
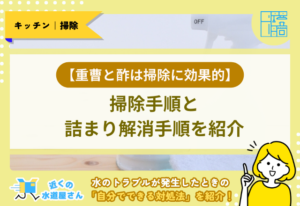
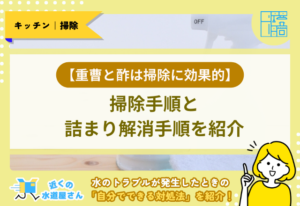
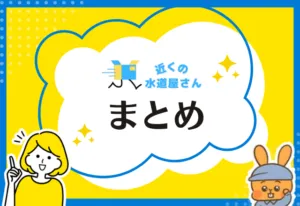
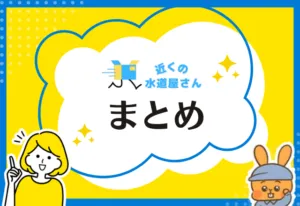
バイオフィルムは排水口の嫌な臭いや詰まりの大きな原因ですが、適切な掃除と日頃のケアでしっかり予防できます。
市販の除去剤やヘアキャッチャーなどのアイテムを活用しながら、定期的に清掃を行うことが大切です。
放置すると再発しやすいため、早めの対策を心がけ、快適で清潔な排水環境を維持しましょう。
何か異変を感じたら、専門の水道業者に相談することもおすすめです。