
近くの水道屋さんが見つかる
ポータルサイト
おすすめの水道修理業者のクチコミや評判を掲載



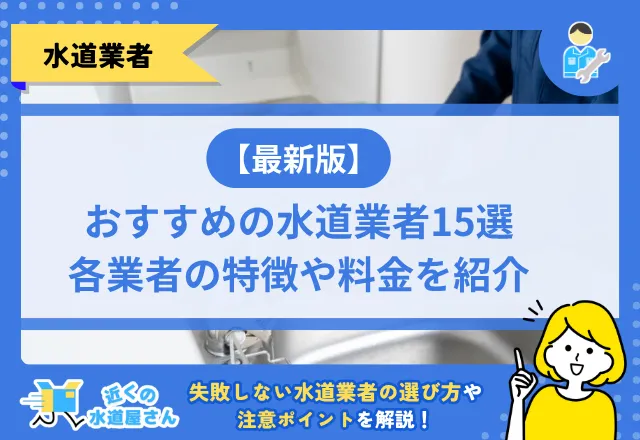
冬場になるとよく耳にする「水抜き栓(みずぬきせん)」という言葉。
特に寒冷地に住む方にとっては、水道管の凍結や破裂を防ぐために欠かせない設備です。
しかし、「そもそも水抜き栓って何?」「どうやって使うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
 ビアス
ビアスこの記事では、寒冷水抜き栓の役割や仕組み、使い方を解説していきます。



水抜きを行わないリスクについても紹介するから、水抜き栓について気になる人はぜひ最後まで読んでみてや!


水抜き栓とは、水道管の中に残っている水を外に出すための「栓(せん)」のことです。
冬の寒さで水道管が凍ると、水が凍って膨張するため、水道管が割れたり破裂したりすることがあります。これを「凍結破裂」と言います。
水抜き栓を使って水道管の中の水を抜いておくことで、水が凍っても膨らむ水がなくなるため、水道管を壊さずに済みます。つまり、水抜き栓は「水道管を凍結から守るための大切な装置」なのです。
水が凍ると体積が約10%も増えます。この膨張した水が水道管の内側から強く押すため、水道管が割れてしまうのです。
水抜き栓を開けて水を抜くと、水道管の中が空になり、水が凍っても膨らむものがありません。これにより、水道管が凍結しても割れるリスクがぐっと減ります。
また、水抜き栓は水道管の途中に設置されていて、通常は閉じていますが、冬の始めや長期間家を空ける時に開けて水を抜きます。
「止水栓(しすいせん)」は、水の流れを止めるための栓で、水道を使う・使わないの切り替えに使います。
例えば、水道管の修理や蛇口の交換をする時に止水栓を閉めて水を止めます。
一方で「水抜き栓」は、水を抜いて水道管を凍結から守るためのものです。名前が似ているので混同しやすいですが、役割が違うため注意が必要です。
まとめると、
この違いを覚えておくと、冬の水道トラブルを防ぐのに役立ちます。


水抜き栓は、特定の状況や季節に使うことで水道管のトラブルを防ぐ役割があります。特に寒い地域や長期間家を空ける場合には欠かせません。
ここでは、水抜き栓が必要になる代表的なケースをわかりやすく解説します。これを知っておくことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して水道設備を守ることができます。
水抜き栓が特に必要なのは、北海道や東北などの寒い地域です。冬になると気温が氷点下に下がり、屋外や壁の外にある水道管が凍ってしまうことがあります。
凍った水道管は破裂しやすく、修理には時間も費用もかかります。
そこで、水抜き栓を使って水を抜くことで、管の中の水が凍らず、破裂を防ぐことができるのです。寒冷地に住んでいる方は、冬の前に必ず水抜き栓の操作を覚えておきましょう。



寒冷地では寒冷地仕様の水回り設備が一般的です。
寒冷地仕様の水回り設備について知りたい方は以下の記事を参考にしてみてくださいね。


旅行や出張などで長期間家を空けるときは、水抜き栓を使うことが大切です。特に寒い季節に不在にすると、家の中の水道管に残った水が凍ってしまう可能性があるためです。
水抜き栓を使って水を抜いておけば、凍結による水道管の破損を防げます。帰宅したら、水抜き栓を閉めて水を元に戻す操作も忘れないようにしましょう。
庭や駐車場、物置などにある屋外の水道や蛇口も凍結しやすい場所です。こうした場所の水道管には水抜き栓が設置されていることが多いです。
屋外の水道は使わないときは必ず水抜き栓を開けて水を抜き、凍結による破裂を防ぎます。使う前に水抜き栓を閉めて水を通す操作も必要です。これを毎年繰り返すことで、水道トラブルの心配を減らせます。
もし水抜き栓での凍結対策を怠ると、まず「蛇口を捻っても水が出ない」ということが起こります。
こうなると水道管を保温するなどして氷が溶けるのを待たなくてはならず、その間は水が使えないため非常に不便です。
また、水道管が凍結してしまうと水が出なくなるどころか、水道管が破裂して大きな水漏れの原因になることも。
ひとたびこれらの問題が発生すると修理費用もかかり、もし水道管が破裂した場合は数十万円以上になることもあります。
このような事態を防ぐためにも、水道管の凍結対策は必ず行っておきましょう。
水抜き栓以外の水道管の凍結対策として、次のような方法もあります。
とはいえ、これらの対策をとっても凍結を完全に防ぐことはできません。
やはり、水を抜いておくことがもっとも有効な凍結防止策です。


水抜き栓にはいくつかの種類があり、設置場所によって特徴や使い方が異なります。
まずは自宅にどんな水抜き栓があるのか、その種類と具体的な設置場所をしっかり確認することが大切です。
ここでは代表的な水抜き栓のタイプと、よく見られる設置場所の例をわかりやすく解説します。
水抜き栓には、大きく分けて次の3種類があります。
手動タイプの水抜き栓は、1か所にあるレバーやバルブを手で操作することで、家中の水道管から水を排出できる仕組みです。
浴室や洗面所の排水口付近、トイレの床面など、水まわりの最も低い場所に設置されていることが多く、冬場の凍結対策として利用されます。
電動タイプの水抜き栓は、スイッチやリモコンで操作できる便利な装置です。
手動での操作が難しい場合や、定期的に水抜きを行う必要がある場所で使われることが多く、リモコン操作だけで簡単に水を抜けるため非常に便利です。
ただし、価格が高めで、定期的なメンテナンスが必要なこともあるため、導入前にはその点も考慮しましょう。
このタイプは、浴室や洗面所、トイレなど、それぞれの水まわりごとに独立した水抜き栓が設置されていて、個別にレバーを操作して水を抜きます。
必要な場所だけをピンポイントで水抜きできるため、効率的でムダが少ないのが特徴です。細かく管理したい場合におすすめのタイプです。
水抜き栓は住宅の屋内と屋外、それぞれに設置されていることがあります。具体的にどんな場所にあるのか、代表的な例を見てみましょう。
庭や駐車場にある蛇口のすぐ近くに設置されていることが多いです。凍結しやすいため、水抜き栓があるかどうか確認し、冬前には必ず水を抜きましょう。
家の外壁の下や側面に配管が通っている場所にも水抜き栓が設置されている場合があります。冬に水道管が凍らないよう保護するためのポイントです。
寒冷地では、室内の水道管も凍結の恐れがあるため、浴室や洗面所の床下や壁際に水抜き栓が設置されることがあります。
トイレの排水口近くにも設置されていることがあり、ここから水抜きを行います。
自宅に水抜き栓が設置されているかどうかを調べるには、以下の方法を試してみましょう。
庭や駐車場の外壁付近、蛇口の根元を確認します。小さなレバーや栓が見つかれば、それが水抜き栓の可能性があります。
浴室、洗面所、トイレの床や壁の近くを見て、水抜き用のレバーや栓がないか探します。寒冷地では特に設置されていることが多いです。
マイホームの説明書や建築図面には、水抜き栓の設置場所が記載されていることがあります。
賃貸住宅や分譲住宅の場合は、管理会社や水道業者に問い合わせて確認してもらうと確実です。


水抜き栓は季節や状況に応じて使い方が異なります。特に冬の凍結防止はもちろん、長期間家を空けるときの準備や日常のメンテナンスにも重要です。
ここでは、季節ごとやさまざまなシーンに合わせた水抜き栓の正しい操作方法をわかりやすく解説します。
具体的な手順や注意点を押さえて、安心して水道設備を守りましょう。
水抜き栓を使う際には、次の点に注意しましょう。
使用する前に、必ず水道を止めてから行ってください。
一見当たり前のようですが、意外とこの作業を忘れて大惨事になったりします。
水抜き栓を開けた際に出てくる水は、錆びや異物が混じっていることもあります。
最初に出てくる水は捨て、きれいな水が出るまで十分に流しましょう。
手動の水抜き栓の使い方の手順は次のとおりです。
まずは自宅の水抜き栓がどこにあるのかを探してみましょう。
水抜き栓には、専用のレンチなどで開けられるねじ、もしくはハンドルがあります。
適切な工具を使って内部のバルブを取り出してください。
バルブを取り出したら、右回りに最後まで回します。
その後、蛇口をすべて開けて水を抜きます。
10〜15分ほど待ち、水が抜けきったら蛇口をすべて閉めましょう。
再び水を通す場合は、蛇口がすべて閉まっていることを確認し、バルブを左回りに最後まで回します。
その後蛇口をゆっくり開けて通水しましょう。
戸建ての場合は、水道メーターから家の内部に入る水道管路に水抜き栓が取り付けられています。
水抜き栓のバルブを最後までまわして水を抜きましょう。
注意点として、バルブは必ず「全開」か「全閉」のどちらかで使うようにしてください。
中途半端な位置で止めると、排出口から常に水がちょろちょろ出つづける状態になってしまうので注意しましょう。
マンションの場合も、基本的には戸建てと同様に水抜き栓を操作します。
右回りにまわして水を抜き、左回りにまわして通水する流れですね。
マンションでは1階の部屋や木造など、冷えやすい場所は凍結の可能性も高いため注意が必要です。
ただし、マンションの場合は水抜き栓の設置場所が共有スペースにあったり、各部屋にあったりとさまざまです。
もし探せない場合は、管理会社や大家さんに連絡するのが確実ですよ。
電動の水抜き栓の使い方について、戸建てとマンションの場合を見ていきましょう。
水抜き栓は、水道メーターから家の内部に入る水道管路に取り付けられています。
電動水抜き栓の機能を使う場合は、蛇口を開けたあとに電源を入れ、水抜き開始のボタンを押しましょう。
水抜きが完了すると自動的に電源が切れるので、蛇口を閉めて完了です。
なお、戸建ての場合は専用の電源が必要になるため注意してください。
マンションの場合でも、戸建てと基本的に同じ使い方です。
蛇口を開けたあとに電源を入れ、水抜き開始のボタンを押しましょう。
水抜きが完了すると自動的に電源が切れるので、蛇口を閉めます。
なお、マンションの場合は一般的にマンションの管理会社が設置しているケースが多くみられます。
そのため、まずは管理会社に確認するのがおすすめです。
水抜き栓を使って水を抜いても、家の中の水道管にはまだ水が残っているかもしれません。
完全に水を抜くために、今度は各水まわりの水抜き栓の処理をしていきます。
各水回りの水抜きは、大本の水抜き栓を閉めてから行います。
また、作業前には必ず給水を止め、排水後は元に戻すのを忘れないようにしましょう。
キッチンでは水・お湯両方の蛇口をまわし、残っている水を出し切ります。
レバー式の蛇口であれば左右に振り、壁付きの蛇口であればドライバーでネジをゆるめてきっちりと排水しましょう。
もしシンク下にも水抜き栓(止水栓)があれば手でまわして排水し、排水後は元に戻すのを忘れないようにしてください。
普通の蛇口がついているケースもあるため、そのときはバケツなどで水を受けて排水しましょう。
お風呂では蛇口・シャワーの水やお湯をすべて出し切ります。
シャワーヘッドは下に置いておくと水が抜けていきます。
蛇口はドライバーでネジをゆるめ、水とお湯の両方を排水してください。
水抜き栓は、お風呂の床面の中央部分にあります。
お風呂への給水管からの水の供給を止めたら、水抜き栓を手で回して水を排出しましょう。
排出後は元に戻して給水を再開してください。
洗面所でも水・お湯両方の蛇口をまわし、残っている水を出し切りましょう。
蛇口がレバータイプなら左右に振り、壁付きタイプならドライバーでネジをゆるめて水を抜きます。
水抜き栓が洗面台の下にある場合は手でまわして排水し、排水後は元に戻してください。
洗濯場では洗濯機につながっている蛇口とホースを外し、水を出し切ります。
ホースを付けるための金具も指で押して排水しましょう。
このとき、水を受けるバケツを用意しておくとスムーズです。
洗濯場の水抜き栓は洗濯機の下や側面に設置されています。
洗濯機に給水する際には給水バルブを開き、排水する際には水抜き栓を手でまわして水を排出します。
排出後は元に戻してください。
トイレの場合は、タンク内の水をすべて抜かなくてはなりません。
ひたすらレバーをまわし、水が流れてこなくなるまで続けましょう。
もし数日家をあけるようなら、ホームセンターで車用のウォッシャー液を買ってきて入れておくと、不凍液のため凍結が防げますよ。
水抜き栓は、主にトイレの床面に設置されています。
トイレ本体への給水管からの水の供給を止めたら、水抜き栓を手でまわして水を排出します。
排出後は元に戻し、給水を再開してください。


水抜き栓が動かなくなってしまった場合、以下の対処法が考えられます。
水抜き栓が動かない場合、まずは取扱い説明書などで正しい操作方法を確認しましょう。
水抜き栓の種類によって操作方法が異なるためです。
また、操作方法が間違っていると、栓が締め切られていると誤解してしまうこともあるため注意してください。
操作方法が正しいにもかかわらず、水抜き栓が動かない場合は、専門の水道修理業者に相談してみるのがおすすめです。
水抜き栓は水道管に設置されているため、素人が勝手に修理することはできません。
経年劣化により、装置が固まって動かせなくなっていることもあります。
このように水抜き栓が故障している場合は、修理ではなく交換が必要なケースもあります。
まずは水道修理業者に相談し、修理がいいのか交換がいいかの判断をしてもらいましょう。


普段から自分で水抜き作業をしているため、交換や設置もDIYでできるだろう!と考える人もいるかもしれません。
しかし、水抜き栓をDIYで交換・設置するのはやめましょう。
前提として、水抜き栓の交換や設置には専門知識と技術が必要です。
不正確な取り付けや作業ミスによって、水漏れや破裂などの事故・トラブルにつながることも考えられます。
また、水抜き栓には水道法に基づいた設置基準があるため、これに準拠しなければなりません。
素人がDIYで交換・設置を行ってしまうと、知らないうちに法令違反になる可能性もあるため、経験豊富な業者に依頼するのがおすすめです。
もし水抜き栓を誤った方法で交換・設置すると、次のような危険が考えられます。
作業時は水道管内の水を完全に止めなければなりません。
しかし、素人がDIYで行った場合、水道管内に残った水が漏れ出し、浸水被害を引き起こす可能性があります。
また、水抜き栓の取り付け位置や向きを誤ると正しく水が抜けず、水圧の低下や水漏れの原因になることも考えられます。
水抜き栓は、水道管内の圧力を正確に計測する装置です。
DIYで交換・設置した水抜き栓が正確な圧力を計測できない場合、水漏れや管の破損、水圧の低下などの原因となり、トラブルが発生する可能性があります。
以上のような危険性があるため、水抜き栓の交換・設置はDIYではなくプロの業者に依頼するのがおすすめです。
水抜き栓の交換が必要になったときに気になるのが、業者に依頼する場合の費用相場ですよね。
かかる費用としては次のものがあります。
一般的な水抜き栓の本体価格は、500円〜2,000円程度が相場です。
高いものでは5,000円以上することもあります。
ホームセンターやAmazonなどで購入できますし、業者に依頼することも可能です。
機能や材質、メーカーによっても価格は異なります。
一般的な相場としては、工事費込みで25,000円〜80,000円程度です。
ただし、交換する場所の状態や作業の難易度によって費用が変わることもあります。
地域や業者によって価格は異なるため、目安として考えてくださいね。
水抜き栓を交換・設置するときは、業者選びにも気をつけてください。
業者選びのポイントは次のとおりです。
業者の選定にあたっては、信頼性や実績が重要なポイントです。
過去の施工実績や口コミ、評判などを調べ、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
費用面も重要なポイントです。
とはいえ、中には費用の削減のため手抜き工事を行う悪徳業者も存在します。
たとえ安くても、手抜き工事をされてしまっては本末転倒ですよね。
見積もりは必ず複数の業者から取り、料金や工事内容を比較した上で、適正価格での工事を提供している業者を選ぶようにしましょう。
施工保証やアフターサポートの有無も確認しておいてください。
もし水抜き栓交換・設置後に問題が発生した場合、業者によっては工事後のアフターフォローが不十分であったり、保証期間が短かったりすることも。
工事後のフォローや保証期間がしっかりしている業者なら、安心して依頼できますよね。
以上のポイントを踏まえ、水抜き栓の交換・設置時には適正な価格で信頼できる業者選びをしましょう。





水抜き栓に関してよくあるQ&Aをまとめました!



時間に余裕のある人はぜひチェックしてみてや!
水抜き栓を閉めたのに水が出てくるのはどうしてですか?
以下の要因が挙げられます。
いずれも水抜きがしっかりできていないと凍結を招く恐れがあるため、1度専門の水道業者に相談することをおすすめいたします。
賃貸住宅でも水抜きを行う必要があるのですか?
必要です。万が一水抜きを怠ったことで水道凍結し、配管が減烈した場合管理会社に修理費用を請求される可能性があります。
入居前に水抜きの説明があったか、契約書に記載がないか等確認しておきましょう。
水抜きをした後トイレの便器内に水が溜まっているのは正常ですか?
トイレの便器内には、排水トラップの封水として水が残る設計になっているので問題ありません。
トイレの水抜きで重要なのは、タンク・配管内の水抜きとなります。
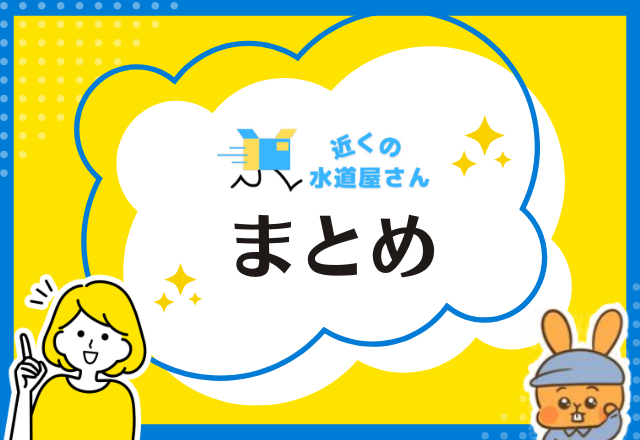
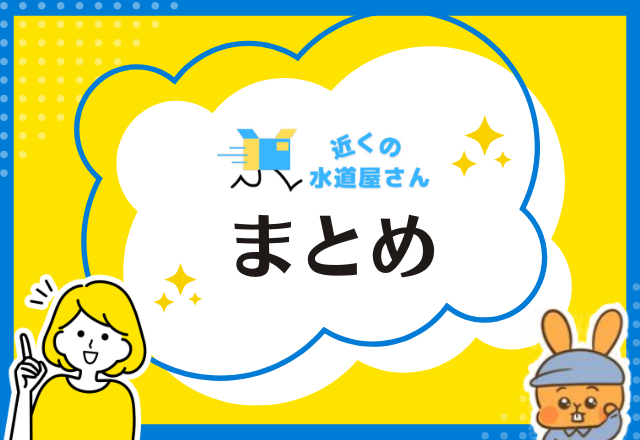
本記事では、水抜き栓の種類や使い方、水抜き栓が重要な理由についてお伝えしました。
寒冷地では水道管の凍結・破裂防止のため、水抜き栓設備は欠かせません。
一般的に氷点下4℃以下が凍結の目安とされており、氷点下10℃を下回るとかなり危険ラインと言えます。
水道管が露出している部分にヒーターを当てたり、家の中全体を暖めりといった工夫で乗り切っていますが、億劫がらずに確実に水抜きを行うことがもっとも安全な方法です。



水抜き栓の仕組みや使い方を理解し、正しく使って安全かつ安心な水回り環境を実現しましょう!



もし水抜き栓の交換・修理が必要になったときはDIYはせず、僕ら水道修理業者に相談してな!